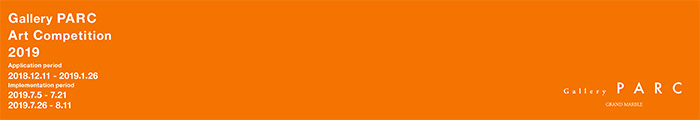募集期間
2018年12月11日(火) ─ 2019年1月26日(土)
応募総数
64プラン
審査員
平田剛志(美術批評)、勝冶真美(京都芸術センタープログラム・ディレクター)
採択プラン(作家・プラン詳細についてはリンク先よりご覧いただけます。)
【 展覧会実施期間:2019年 7月26日(金)~8月11日(日)】
■「アンバー・ランド」 出展作家:洪亜沙 形式:個展(インスタレーション)
【 展覧会実施期間:2019年 7月5日(金)~7月21日(日)】
■2階 「部屋と外」 出展作家:加藤舞衣 形式:個展(版画)
■4階 「キャンプができたらいいな。」 出展作家:坂口佳奈・二木詩織 形式:二人展(インスタレーション)
*なお、応募資料の郵送・直接の返却は3月半ばよりおこないます。
6年目となる本年の公募は、国内外から64件のプランが集まりました。
例年以上に質の高いプランが多く難しい審査となりましたが、長時間に渡る審査を経て、フロア全体を使った1プランと各フロアを使用した2プラン、計3名(組)を選出しました。選外のプランにも魅力的なものが多くありましたが、またどこかでご一緒できる機会を楽しみにしています。
今年の応募プラン全体の印象は、言葉の抽象性、難解さでした。今に始まったことではありませんが、展覧会タイトルやエントリーシートには、硬い言葉や専門用語が並び、学術論文を思わせるプランも散見されました。
そもそも展覧会とは誰に向けて作られるのでしょうか。美術とは美術館学芸員や大学の研究者などアカデミズムに向けてつくられ、見られるものなのでしょうか。
言うまでもなく抽象的な言葉でしか語れないこともありますが、結果的に入選したプランは作品をどのような展示で見せるのかが具体的でわかりやすく記述され、清新な驚きと感銘を与えてくれました。
洪亜沙「アンバー・ランド」
作家の創作による物語「アンバー叙事詩」をもとにした遺物や考古資料による博物館展示、イコンをテーマにした宗教的空間による2部構成の展示プランは、本コンペ中、類を見ない世界観でした。セカイ系にも通じる神話的な物語と博物館展示とが緻密に融合され、現実と虚構、過去と現代の境目を曖昧にする多視点的な構成には瞠目しました。新たな年号=歴史が始まる本年、洪亜沙はどのような物語=歴史を虚構空間化するのでしょうか。
加藤舞衣「部屋と外」
加藤のプランは、部屋の壁に貼られたテープ跡、路上に落ちているものをモチーフにしたリトグラフ版画です。誰もが見落としている壁面や路上の痕跡、経年変化という時間作用にリトグラフの化学作用による製版を見出す加藤の視点には版画的な思考が息づいていました。デジタル社会の現代、壁や路上に残されたアナログなグラフィティの痕跡をリトグラフへと変換する加藤の版画に私たちは何を発見するのでしょうか。
坂口佳奈・二木詩織「キャンプができたらいいな。」
東京在住の坂口佳奈と二木詩織の二人は、制作した作品を搬入するのではなく、東京から京都へ向かう道中で制作したものをインスタレーションやパフォーマンス、絵画として展示するプランです。特筆すべきは旅行計画でした。キャンプで焚き火や釣りをし、サービスエリアでソフトクリームを買い、京都の金閣寺でセルフィーを撮るなど、およそ展覧会とはかけ離れたナンセンスさが爽快でした。YouTuberが実験や検証をする「やってみた系」動画のようなプランですが、果たして彼女たちは無事にキャンプができるのでしょうか。夏の京都、二人の無事の到着を心待ちにしています。
平田剛志 (美術批評)
本コンペティションの審査を担当して3年目となりました。年々、審査の難しさを感じています。それは応募者の世代がこれまで以上に幅広く、またこれまで絵画が多い印象だったメディウムも、より多様になってきているということもありますが、「審査」という行為そのものの曖昧さ、危うさのようなものに今更ながら気づかされたからかもしれません。
熱のこもったアーティストからのプランを前に、何か統一した基準をもって審査することはますます難しく、審査は(毎年のことですが)長時間に及びました。最終的には、「見たい」という審査員のシンプルな欲求に対し、その背中をぽんと押ししてくれるような企画を選出することとなりました。今回選出した3つのプランからは、どれもそういった力を感じました。
自身がつくりだした架空の物語を作品化するという洪亜沙さん。彼女のつくり出そうとする確固たる虚構のありようが魅力的ですが、私たち人間がいかに物語を必要とするのかについて考える機会ともなりそうです。加藤舞衣さんは、壁に残るテープの痕や道に落ちているものなど、人知れずそこにあるものに目を向けます。それらがアーティストを介して展示空間に持ち込まれるとき、鑑賞者それぞれの忘れられていた物語が立ち現れるでしょう。坂口佳奈さん・二木詩織さんは、二人が住む東京から京都までを実際に移動することから作品を制作するという。新幹線だと2時間程、もはや当たり前となったこの距離と時間をどう想像しなおせるのでしょうか。
まだ見ぬものたちが一体どんな展示となってあらわれるのか、今から楽しみにしています。
勝冶真美 (京都芸術センタープログラム・ディレクター)