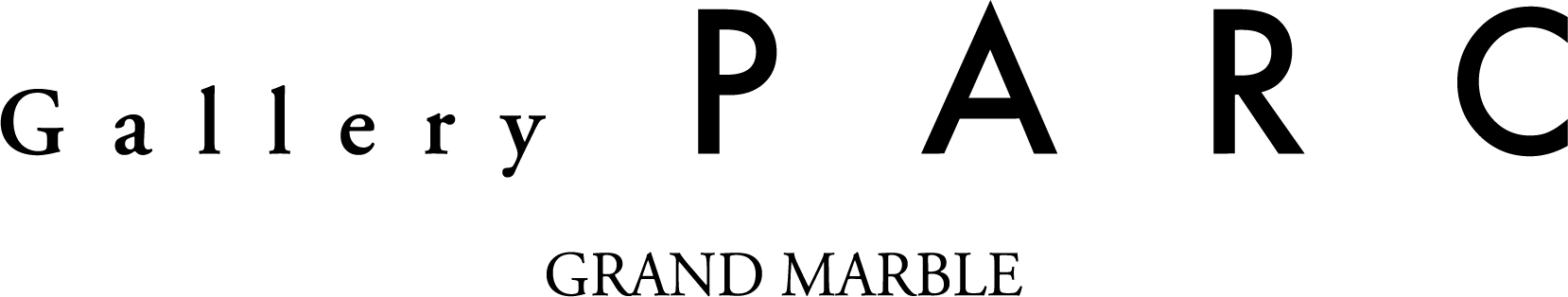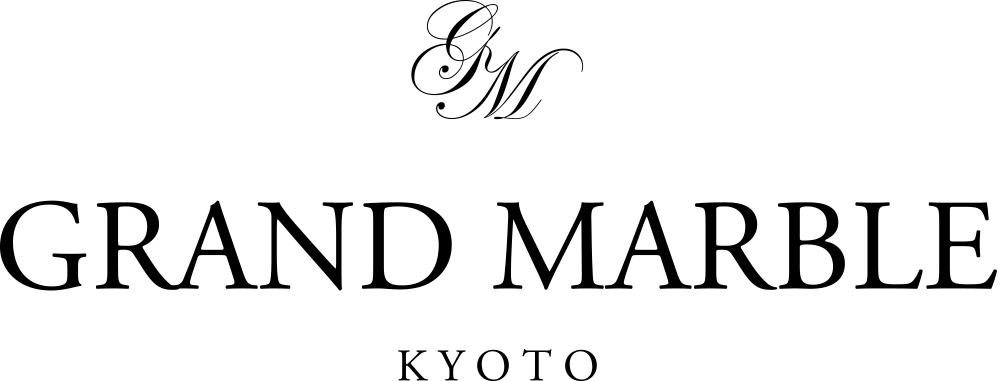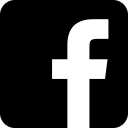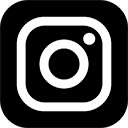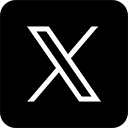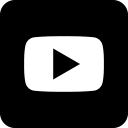Akira Kazuki
Exhibition info
Gallery PARC Art Competition 2015 #03
2015.7.31. 〜 8.9.
Statement
私は色を置くこと、与えることで作品を成立させています。
展覧会について
ギャラリーをホワイトキューブ化する。
関連テキスト
抽象画、風景画、宗教画、太古の壁画。描かれている内容、描かれた時代、描くのに用いた素材が異なったとしても、それらの「描く」行為を「色を置いている」と捉えてみる。その置き方には、その時代や場所、状況によって必然性が存在する。
明楽の作品は、非常に感情的であったが大学で現代美術を学び始め、徐々に理性的になっていく。その過程で作品にメッセージ性を与えることをしなくなり、タイトルも16LB(16個の電球)、24colors(24色の絵画)など、作品をシンプルに表したものとなっている。また、彼は空間や物から、色や、その並べ方、ルールを決めていく。時に、それはビー玉を床に落としたり、色鉛筆を並べたり、カラフルなシャボン玉が宙を舞ったりする。そこにはその対象から紡ぎ出され、高められた必然性がある。
今回の個展「白」ではギャラリーをホワイトキューブ化する。それは展示空間において、ある意味、当たり前の状況を造ることであり、美術館やギャラリーでは見慣れたものだ。しかし、ことPARCで言えばいままでにないほどに空間が異化され、白壁に囲まれて物質的には満たされた場になるが、美術の制度として、観るものが何も無い、という異様な状況が創り出されるだろう。
About
Gallery PARCでは、様々なクリエイション活動へのサポートの一環として、広く展覧会企画を公募し、審査により採択された3名(組)のプランを実施するコンペティションに取り組んでおります。昨年に引き続き2回目の実施となるGallery PARC Art Competition 2015 において、応募いただいた34のプランから、平田剛志(京都国立近代美術館研究補佐員)、山本麻友美(京都芸術センタープログラムディレクター)の2名の審査員を交えた厳正な審査を経て採択された田中秀介、中尾美園、明楽和記の3名による展覧会を連続で開催いたします。本展「明楽和記:白」はその第三弾となります。
2011年に成安造形大学構想表現クラスを卒業、2012年に(今井祝雄研究室)を修了した明楽和記(あきら・かずき/1988年・和歌山生まれ)は、これまで京都・大阪での個展やグループ展などで発表を続け、2014年には「ART COURT FRONTIER #12」(ART COURT GALLERY・大阪)に出品するなど、精力的な活動を続けています。
『私は色を置くこと、与えることで作品を成立させています。』とする明楽は、これまで物や場が持つ性質や特性を見極めながら、それらと関わる際に「色彩」という要素に着目した作品を多く発表しています。たとえばラッカーで塗装され、その機能を奪われた既製品の時計は、単なる「色」を機能として壁面に配置され、カラフルなスーパーボールは跳ね回って空間にストロークを描き続け、大量のビー玉は床にドリッピングされます。また、木目に沿ってランダムに選択した色を与えられた30本の角材は並べられ、空間と絵画を同一の存在に肉薄させます。
明楽によるこれらの試みは、所謂サイト・スペシフィックなインスタレーションとして回収される点も多いかもしれません。しかし、本質的にその多くは明楽が「絵画」を解釈・分解することでその諸原的要素を抽出し、支持体として目の前の空間の意味や特性を観察し、その場に捉えたものを描き出す(露にする)ための行為とも呼べるものです。言い換えるとこれは絵筆を持たずに絵画に取り組むものであり、目の前に残る色はそのアプローチの軌跡が描き出された絵画を成すものであるといえます。
本展『白』は、ギャラリー・パルクの空間をホワイト・キューブ化させるというシンプルなものです。「白い立方体」と訳されるそれは、アーティストの様々な表現を提示する空間において、中立的で無個性を象徴する白によるシンプルな箱型の設えの代名詞として、一般的な展示空間に多くみられるものです。そして、打ちっぱなしのコンクリートによる柱や壁、東南に面して大きなガラス窓を持つギャラリー・パルクは、いわばこのホワイト・キューブという様相に反し、多くの要素が混在するスペースとして特異なものと言えます。
明楽が此処に白によって関わるこの行為は、「白」という色彩により「無」を描き出す行為でもあり、美術の制度において「観るべ」の空間を作品として提示するものであるとも言えます。此処に鑑賞者は何を「観る」でしょうか。
作家情報について詳細はこちらよりご覧ください。 >Artist info
Review