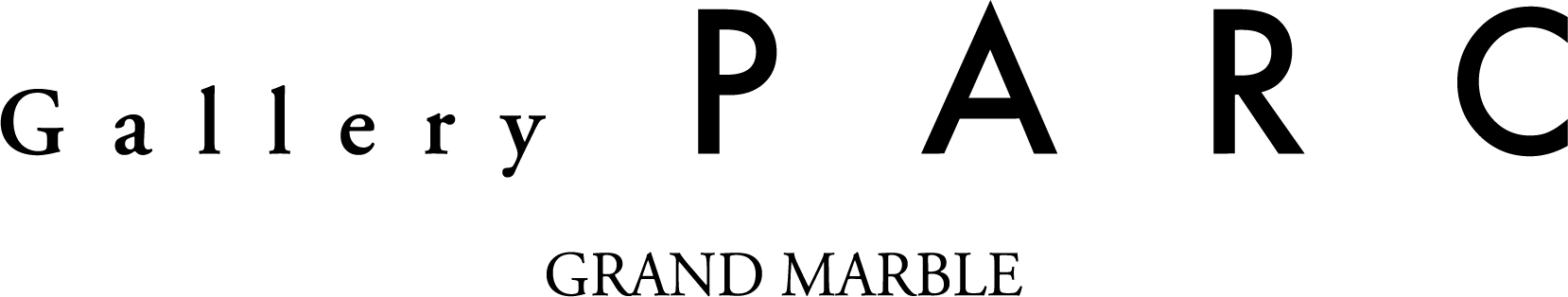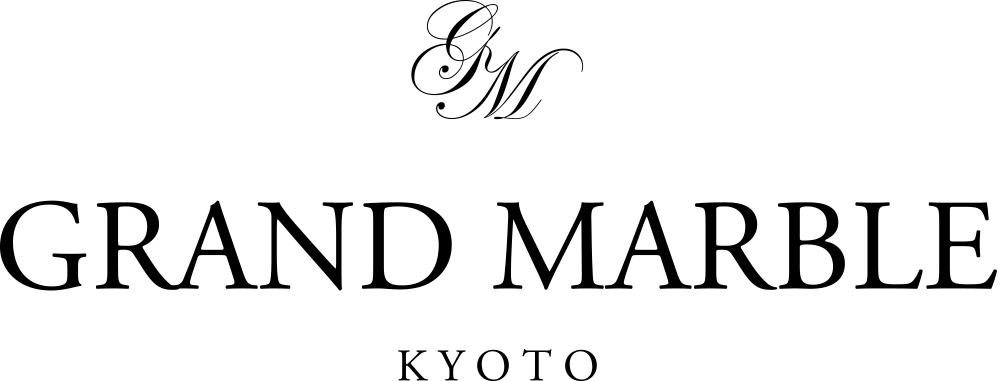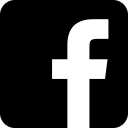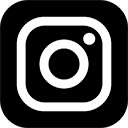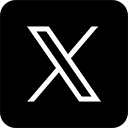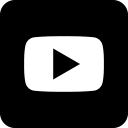Gallery PARC Art Competition 2015
「明楽和記:白」展示風景
白からはじまる
平田剛志(美術批評 / Gallery PARC Art Competition 2015 審査員)
展覧会は白からはじまる。だが、本展でなにが展示され、なにを見たのか、見る人によって異なるかもしれない。明楽和記の個展「白」は、展覧会企画公募「Gallery PARC Art Competition 2015」で選出された展覧会として開催された。その展示プランは「ギャラリーをホワイトキューブ化する」内容であった。そう、観客が展覧会で見ることになる「白」とは、「ホワイトキューブ」なのである。まっ白な壁やホワイトキューブを前にしたとき、人はそこにどのような感情を喚起し、どのような言葉を発することができるのだろうか。そのもどかしさや困惑を言葉として記述を試みるのが本論である。
言うまでもなく、これまでも「白」を主題とした美術作品はあった。カジミール・マレーヴィチの《白の上の白》(1918)や今井祝雄の《白のイヴェント》(1965)、《白のセレモニー》(1966)などが代表的な作品として挙げられよう。だが、それらの作品は「ホワイトキューブ」のなかで展示される作品であり、「ホワイトキューブ化」を目指したものではなかった。
これまで明楽は「色を置くこと、与えることで作品を成立」させる作品を制作・発表してきた。ただし、明楽が色を「置き」、「与える」場は、キャンバスという平面ではなく、展覧会場の「空間」である。それは、空間を「色彩化」する行為だといえるだろうか。明楽の作品は「「絵画」というルールを参照しながら再構成された「絵画」」【註1】であり、「描かない画家」による「絵画」なのである。例えば、アクリルケースの中でスーパーボールが飛びまわる《An Infinite Stroke (super ball)》(2012)や床にさまざまな色のビー玉を大量に落とした《6,000 marbles》(2012)、30本の角材の木目にランダムに色を着彩し並べた《acow》(2014)など、空間や物質に色彩を配置(放置)するのが特徴である。色彩は次第に「空間から環境へ」と拡張しつつあるが、明楽の作品は色彩を空間と物質との相互作用や偶然によって流動的、可塑的に成立する色彩論または、絵画論の試みともいえるだろう。
そして、今展「白」で明楽が行ったことは「ギャラリーをホワイトキューブ化する」ことだった。これまでの明楽作品に見られた大量の色彩を空間に与える作品からすれば、本展は「異色」の作品に思えるかもしれない。だが、明楽は過去に壁一面に黄色い絵具を塗った《yellow wall》(2011)という作品を制作していることから、本作もまた「白」という「色」を主題とした作品であることに変わりはない。そして、《yellow wall》が平面の「壁」であったのに対し、今展の「白」は「ホワイトキューブ」という立方体の空間形成が目指されているのだ。
続いて、「ホワイトキューブ化」される会場を確認しよう。ギャラリー・パルクは床や柱、壁は打ちっぱなしのコンクリート、東南側には大きなガラス窓があり、壁よりもガラス窓を特徴とするギャラリーである。展示によっては仮設壁の設置が行われ、「ホワイトキューブ」に近い空間が出現することはある。だがそれは展示のためであって、「ホワイトキューブ化」のためではない。
では、そもそも「ホワイトキューブ」とは何なのか。美術館やギャラリーでは、ホワイトキューブ(白い立方体)の展示室が前提ないしは理想とされている。その始まりは1929年に開館したニューヨーク近代美術館(MoMA)がホワイトキューブを採用したことに由来する。それ以前の展示室は、17世紀のオランダ絵画で描かれた「ギャラリー画」に見られるように、室内にコレクションされた絵画が余白を残さずに埋めつくされる展示が主流であった。展示室の壁の下には腰板がはめられ、壁自体も色が塗られるか装飾模様の布が張られ、作品はしばしば2段掛け、3段掛けで展示されたのである。
このような展示手法は19世紀になるにつれ、博物学や美術史の進展・成熟により、作品やコレクションは科学的に分類・整理されていく。さらに、作品は地域や時代、ジャンルによって分類され、時間軸に沿った啓蒙的な展示が成されていくのである。展示空間に装飾的要素は排除され、鑑賞者の注意を作品だけに集中させるニュートラルなホワイトキューブの誕生である。
ホワイトキューブは絵画や彫刻に限らず、どのような作品も対応できる空間である。そのため、世界中どこにでも可能な空間として広まっていく。1970年代以降には額や彫刻の台座を取り去り、空間内に設置される「インスタレーション」を生むことになった。そして、美術作品でないものさえ「アート」に変える力を「ホワイトキューブ」は有するようになるのである。
こうして、多くのアーティストが展示にあたって、ニュートラルで無機的な「ホワイトキューブ」を「理想」として求めるようになった。では、ホワイトキューブではない会場であるギャラリー・パルクに理想の「ホワイトキューブ」が出現したとき、それは理想に適う空間となったのだろうか。
結果として、明楽が本展で試みたのは無個性でどこにでもある「ホワイトキューブ」ではなく、「ここにしかつくれない個性あるホワイトキューブ」だった。その理由のひとつは、会場に漂う絵具の匂い、壁や床、畳を取り外した小上がり部分に残された絵具の塗り跡などに絵画的痕跡が散見されたからである。明楽はギャラリーを「ホワイトキューブ化」したと同時に、「ホワイトキューブ化」した非形象「絵画」を試みたと言えるだろう。かつて、カジミール・マレーヴィチが1913年からシュプレマティスム(絶対主義)を提唱し、白黒の円や正方形のみを構成要素とする「無対象」の抽象絵画を描いたように、明楽はホワイトキューブという描画対象のない「無対象」絵画を描いたのだ。
小林康夫は、「絵画とは、見えるものを見えるように描くことなのではなく、「見えるもの」をたえずその彼方の「見えないもの」と触れ合わせ、その「見えない」ものの領域へと連れて行き、また逆に、「見えないもの」を密かに「見えるもの」の領域へと引き降ろし、物質のうちに受肉させる途方もない営み」【註2】だと定義した。だとすれば、明楽は美術作品を展示する「見えない」制度である「ホワイトキューブ」を「見えるもの」の領域へ置いたといえるだろう。私たちが本展に困惑ないしは苦笑するとすれば、見ていたのに見えないようにしていたホワイトキューブという「制度」を見ることになったからである。ハリボテのような「ホワイトキューブ」が明らかにするのは、白々しいまでの「ホワイトキューブ」の作為性であった。私たちは「理想」の「ホワイトキューブ化」されたギャラリーでなにを見ればいいのか目のやり場に困りつつ、壁の平面に「白」の「絵画」を見ようとする。まるで、白紙の原稿用紙やまっ白い画用紙を突き付けられたように、途方に暮れながら。
【註1】吉田モモコフ「明楽和記個展 『16LB』」
【註2】小林康夫「絵画のアルファとオメガ―表面と拡がり」『色の博物誌・白と黒―静かな光の余韻』目黒区美術館、1998年、15頁。