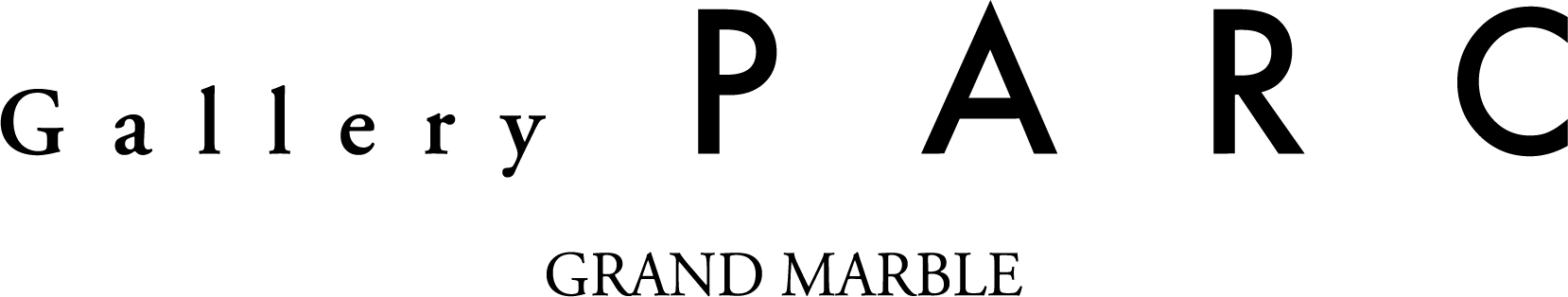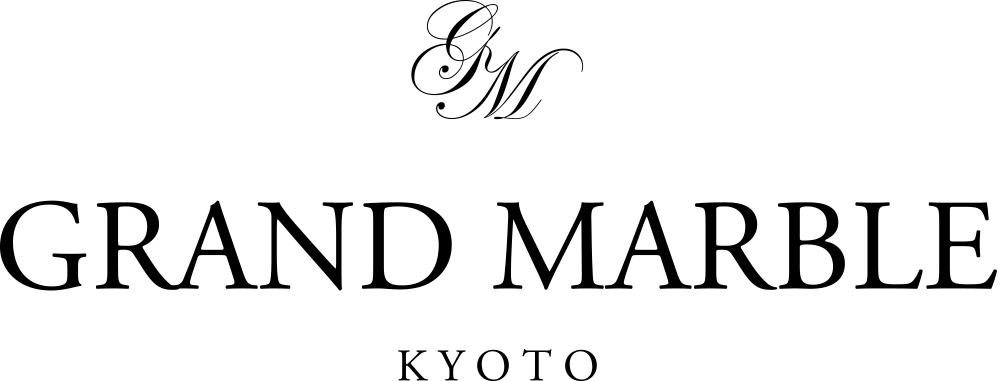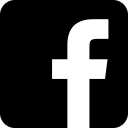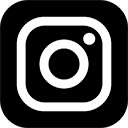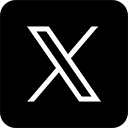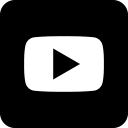Gallery PARC Art Competition 2019
「加藤舞衣:部屋と外」展示風景
何かの痕跡は誰かの行為である
勝冶真美( 京都芸術センタープログラムディレクター / Gallery PARC Art Competition 2019 審査員)
築33年のアパートに住んでいる私の家には、これまでの住人のものであろうシミがいくつも残されている。
まっさらな壁紙の新築マンションとは似てもにつかないその部屋はしかし、新築にはない不思議な親近感があるような気がしている。
「Gallery PARC Art Competition 2019」で64件の応募から採択された加藤舞衣は、主にリトグラフの技法を用いて制作を行なう。本展も含め近年は、道に落ちて踏みつけられた花びらや、壁に残ったテープの跡などをモチーフとし、物とも言い切れないような、朽ちて消えゆく手前のものたちを、繊細な手つきで表出させる。
「物の在り様」を表現したいと話す加藤は、昨年まで通っていた大学の壁をはじめ、自身の身近な場所に残る「何かの痕跡」を、トレースしたり、写真から起こしたりすることから制作を始める。そのものだけではなく、そのものが湛えている経年変化や、自然風化といった現象をも取り込んで、ギャラリーのまっさらな白壁にかけられた作品は、仮設された時間として提示されるようだ。テープの跡は単にテープの跡なのではなく、かつて何かを貼り付けていた糊、貼り付けられていた何か、テープを張った人の仕草、すべてのものの総体として現前するのである。その意味で加藤が表現するものはものではなく行為なのかもしれない。
行為の痕跡を、俯瞰的に観察し作品としてきた加藤が、本展では新たな試みを行った。
会場の3階では、テープの跡が刷られた薄い半透明の雁皮紙が、ビリビリに破かれ、壁一面に無造作にマスキングテープやピンで留められている。聞けば、搬入中に破くことを思いついたという。
フレームは瓦解し、テープの跡は今やあらゆるところに散らばっている。無造作に散らばるそれらは、いつかのあの場所の痕跡であることから離れ、さらに匿名性を増す。テープの跡は、加藤自身の手により、今まさに実際にテープで、あるいは虫ピンでその場にとどめられている。加藤自身の行為が追加されることで、過去から現在が地続きとなり、彼女の視点がよりはっきりと提示されている。
パソコンから目を上げると、壁紙のシミが目に映る。親近感を呼び起こす正体に思いを馳せる。そう、かつて誰かもここに暮らしていたのだ。