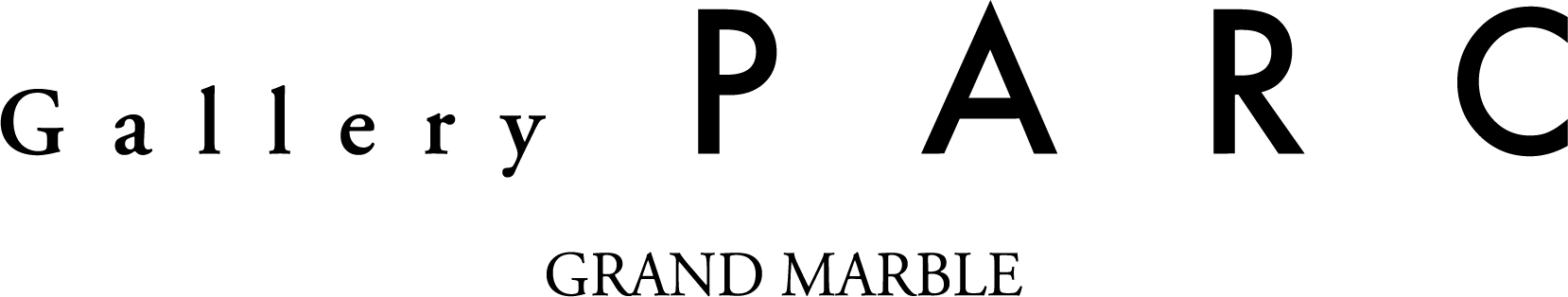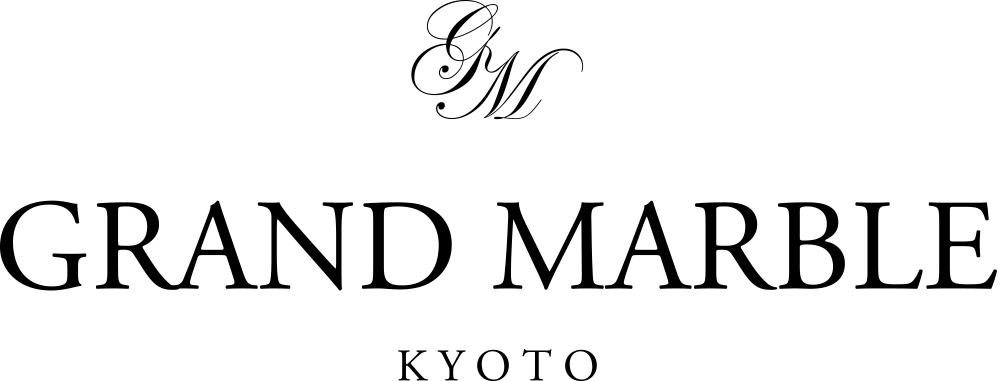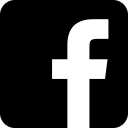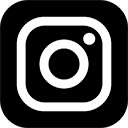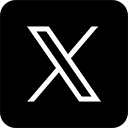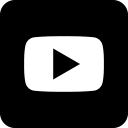Gallery PARC Art Competition 2018
「森岡真央:ママ、きいてちょうだい」展示風景
有題
勝冶真美( 京都芸術センタープログラムディレクター / Gallery PARC Art Competition 2018 審査員)
限りなく単純化した線によるドローイングのような絵画。写真などで森岡真央の作品をみると、そのように感じるかもしれない。ただし、作品に対峙するとその先入観は大きく裏切られる。伸びやかなワンストロークの線だと思っていたものは、実は丁寧に着彩されていて、線というよりは面であることに気づく。
質感から日本画材が用いられていることが分かるが、日本画らしからぬかなり厚みのある線(面)もある。鑑賞者の視線は線から面、面から線へとうつろい、厚みによりもたらされる影もまた新たな線へとなって現れる。イメージを捉えられるような、捉えられないような、不思議な時間の滞留を体験することになるだろう。
この独自のスタイルをつくりだすまでのプロセスは、作家本人が別に記しているのでここで重ねて言及はしないが、対象を写生し、原寸大の下絵をつくり、線を和紙に転写させて線描していく、伝統的な日本画法を学んだ森岡が、大学院時代にスキャニングやデジタル画像処理、また版画にも親しんだことが、独自の手法の獲得に大きく貢献したことは付け加えておきたい。
森岡の関心は常に、絵画におけるイメージのあらわれ方そのものにあり、それはこれまでの作品タイトルがすべて「component of …」とナンバリングされるのみだったことにも見て取れるが、本展では新たな試みとして、作品にタイトル(題)が付与されている。そのタイトルも一筋縄ではいかない森岡節で、3階の展示作品である《 ラ M P 》(ランプ)や、4階の展示作品《 MYDE OHKEYNEE 》(まいど おおきに=招き猫)など、言葉遊びのよう。絵画において対象と描かれたものの「ずれ」を感じさせる部分を大事にしていると本人が語るように、タイトルもまた、文字と意味とイメージの間を行き来する「ずれ」の作用を増幅させる装置となっていて、鑑賞者をさらなるイメージと想像の森へと誘う。
この彼女の挑戦は、彼女の創作における試みをさらに深めるものとなったようだ。
それらのプロセス -作品にタイトルをつけ、展覧会として構成したこと- は一般に作品を成立させる上で当然のことのように思われるが、森岡のこれまでの創作プロセスが、余分を削ぎ落とした先に現れるイメージの立ち上がり方にあったが故に、そこに作品タイトルや展示構成といった横軸を加える作業の意味を一層強固なものにすることに繋がっている。
本展での森岡の新たな展開は、本公募企画が作品公募ではなく、展覧会の企画公募であるという意図への応答であることを思うと、審査員の一人としても素直に嬉しく、新しい出発点となったであろう本展を経た、彼女のこれからの活躍を期待している。