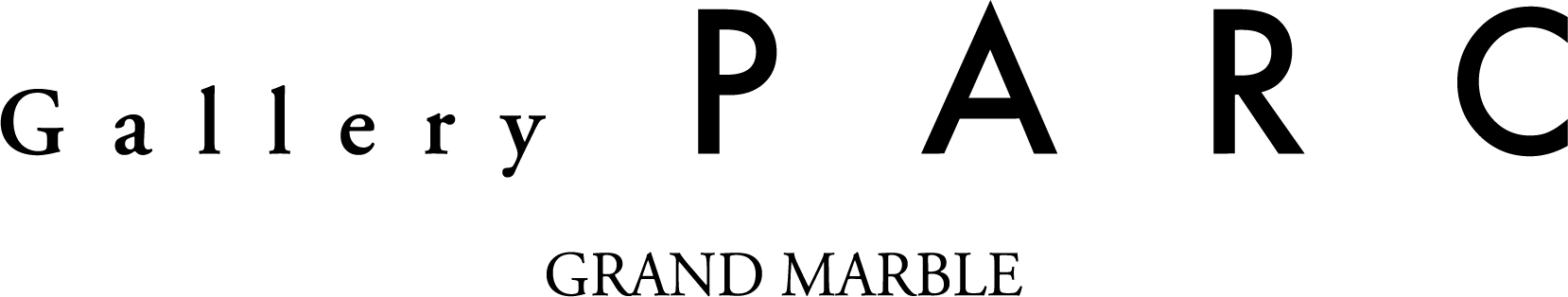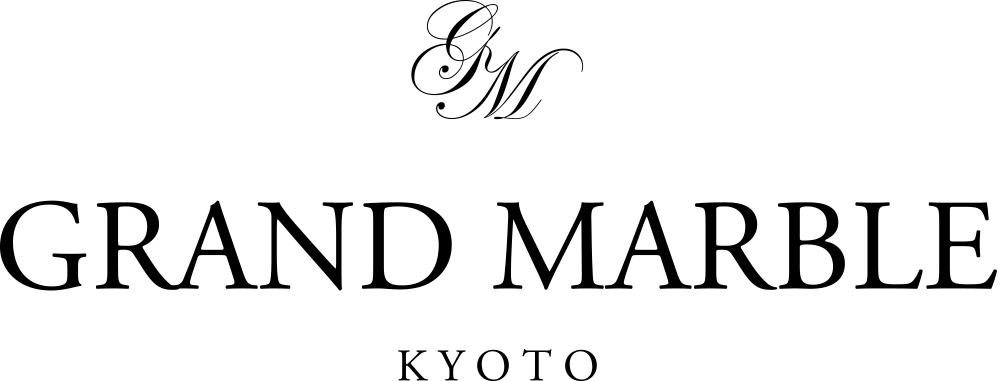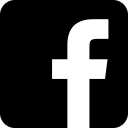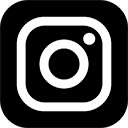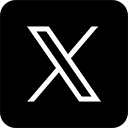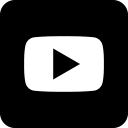Gallery PARC Art Competition 2017
「近藤洋平:whereabouts」展示風景
whereabouts
平田剛志(美術批評 / Gallery PARC Art Competition 2017 審査員)
豪雨のような驟雨に直撃して入った近藤洋平の「whereabouts」は、雨からはじまる。ギャラリー内にステンレス棒を斜めに配置した《通り雨》である。雨を好んで描いた歌川広重の浮世絵に描かれる直線的な雨を思わせ、ステンレスの質感が水の冷たさを喚起する。続く、他の展示作品も硬質で無機質な鉄、コンクリート、トレーシングペーパーなどを素材とする作品が並ぶ。コンクリート塊の内側に封じ込めた電球の光が微かな隙間から漏れ出る《予兆》、厚さの異なる鉄板がコンクリート上に互い違いに並ぶ《分水嶺》など、自然現象や状況のイメージを視覚化した作品だ。
これら近藤の作品は、素材を未加工または僅かな加工によって制作されている点で、本人も言明しているように、もの派の影響を指摘できるだろう。もの派とは、峯村敏明の定義を引けば「1970年前後の日本で、芸術表現の舞台に未加工の自然的な物質・物体を、素材としてでなく主役として登場させ、モノの在りようやモノの働きから直かに何らかの芸術言語を引き出そうと試みた一群の作家たちを指す」【註1】動向である。近藤の作品も、ものが主役である点で、もの派の系譜に位置づけることができるだろう。
また、もの派の具体的な作品との類似も挙げられる。例えば、《通り雨》は、垂直にたてたスティールパイプと平面作品を組み合わせた吉田克朗《赤・スティールパイプ・紙など》(1971)、《予兆》は壁に立てかけたステンレス板によって電球の光が遮断される高松次郎《光と影》(1970)、タイトルは榎倉康二の写真作品《予兆》(1972)を思わせ、《分水嶺》は角材の上に異なる厚さの鉄板をおき、自然なたわみの様相を見せる吉田克朗の《Cut-off No.2》(1969)を容易に指摘できる。
以上の例から、近藤の作品がもの派に強く影響を受けた作品であることは間違いない。だが、近藤作品がもの派からの引き写しかと言えばそうではない。まず、もの派の作家は見立てを用いなかった。彼らは、「日常的な〈もの〉そのものを、非日常的な状態で提示する」ことで【註2】新しい世界を開示したのであって、本展のように「日常で見かける素材を水のイメージに重ね」ることはしていない。
また、もの派の作品の多くが巨大な鉄板や石、土、ガラスなどの単体またはわずかな組み合わせによるインスタレーションであったのに対し、近藤はサイズが小さく細く、点数が多い。《通り雨》は20本のステンレス棒が並び、ステンレスの鏡面に周囲の反射・反映する光景を写し出し、時間によってその様相を変える。《分水嶺》は28枚の鉄板によって構成され、インスタレーションよりも物質性を強く感じる。いずれもステンレスや鉄などの素材の特徴を生かした「彫刻」といえる。
このような素材の性質・特性を生かした加工や見せ方をおこなう近藤の制作姿勢は、大学で建築を学んだ経歴に由来するだろう。今展は、近藤にとって初めての展示空間だが、抑制された出品数と間のある空間構成は空間を読み解く建築経験があるからだろう。一方、建築とはさまざまな素材を使用し、堅牢な空間・構造物を構築することだが、近藤は「この世界の曖昧さや不安定さ」、揺らぎをつくり出すことに関心を見出す。不変的な見え方ではなく、空間が時間や場所、鑑賞者の存在によって変化し、見え方が一定しないこと。近藤はもの派の影響を通じて、「つかみ所(whereabouts)」がない空間や存在をつくり出す。峯村敏明は「すぐれた彫刻はつねに私たちに何らかのやり方で存在感の揺さぶりをかけるという特質をもっている」【註3】と書いたが、近藤の本展の作品にはすぐれた彫刻がもつ揺さぶりをかける特質がある。
大気の不安定さによって突然降りだす通り雨。雨上がりには、空気や気圧、湿度が変わり、空間は変容する。本展に現れた「通り雨」のような近藤の作品は、空間を変える雨だった。雨を降らす雲がかたちを変えて再び雨を降らすように、近藤の作品も私たちに恵みの驟雨をもたらし続けるだろうか。再び、「通り雨」が訪れるその日を待ちたい。
【註1】 峯村敏明「「モノ派」とは何であったか」『モノ派』鎌倉画廊、1986年、[2]頁。
【註2】 「あいさつ」『もの派—再考』国立国際美術館、2005年、6頁。
【註3】 峯村敏明『彫刻の呼び声』水声社、2005年、39頁。