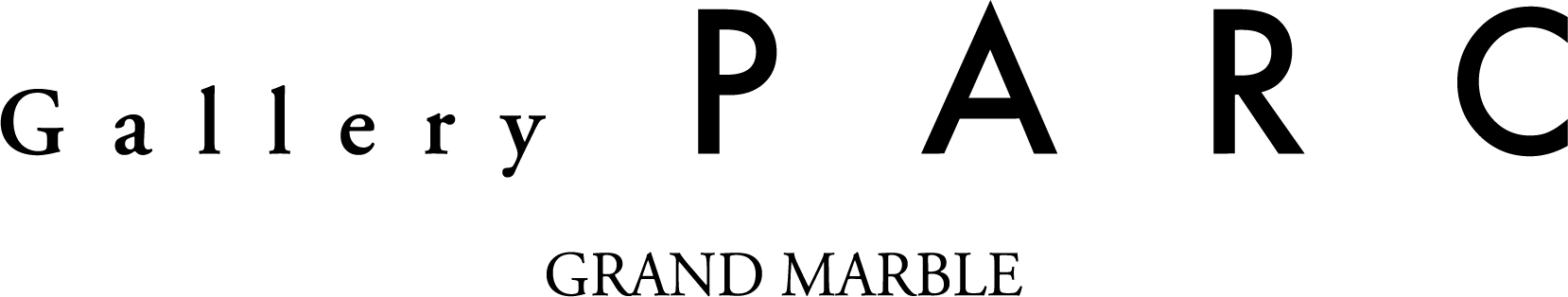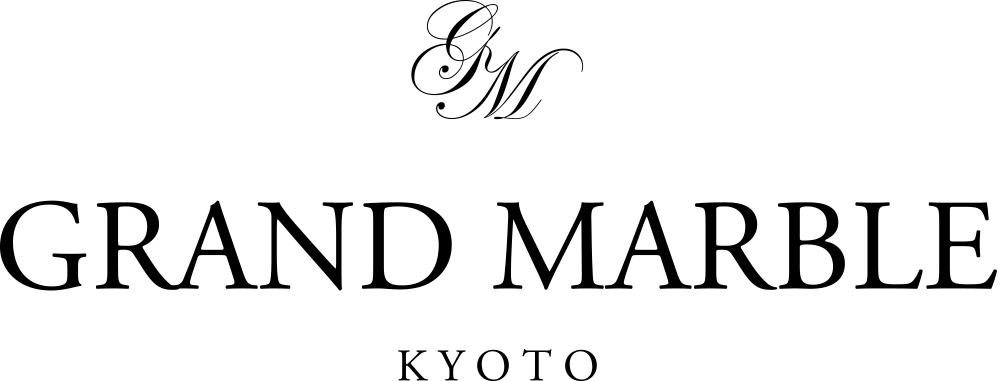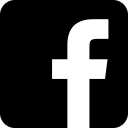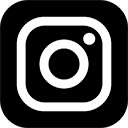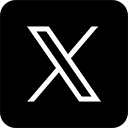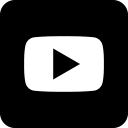Gallery PARC Art Competition 2016
「嶋春香:MEET / MEAT」展示風景
画像という幽霊 ー嶋春香 Touch作品に寄せてー
武本彩子(Gallery PARC)
嶋春香は、京都市立芸術大学大学院在学中より、一部の彫刻作品を除き、「写真(画像)」を見ることを出発点として作品を制作している。「Touch」と名付けられ、現在までの3年間にわたって続けられている一連の作品群は、モチーフに対する作家の数々のアプローチの痕跡である。
***
初期のTouch作品は、インターネットの画像検索で見つけたデジタル画像をモチーフに、単色のみで描かれていた。キーワードをもとに得た画像を、ルーペ等で拡大して見ながら、あるいはキャンバス面に拡大してプロジェクター等で投影した光をなぞるようにして、そこにある質感に「ふれる(=Touch)」かのように、筆で絵具を置いていくことで描かれる。単色の濃淡のみという要素の少なさから、作家の筆致(=Touch)の強弱に注目させるこれらの作品は、画像のもつ「イメージの力」(連想の力と言ってもよい)を、筆で絵具を置くという「具体的な行為の蓄積」に置き換えていった作品ということが可能だろう。兵士が並ぶ画像を描いた作品《Touch #carmine 1》は、本来の画像の向きから90度回転させることで、イメージの持つ強さを瓦解させている。
その後のモチーフの探求の中で、嶋は、博物館や歴史資料館等に保管されている、過去の時代や文明の遺物である民具を撮影した「資料写真」にたどりつく。これらの「資料写真」は、その性質から、一般的には被写体となる民具を客観的に記録することが目的とされる。しかし、被写体となった民具が、我々の生活している文化や時代から大きく隔たった文明に属する場合、機能や意味が容易に想像できない、一種の抽象的存在となる。資料写真をモチーフに据えることで、Touch作品は、作者の恣意的な操作を要することなく、画面に抽象性をもたらすこととなった。資料写真は現在に至るまで主要なモチーフであり続けている。
筆で絵具を置く点描を主体とした描き方から発展し、手やペインティングナイフを使って描くなど、画法のバリエーションに富むようになった嶋の作品は、身体的触覚を探求した彫刻作品の制作を経たのち、紙片や布片をはりつけたコラージュの手法を使った作品となる。さらに、嶋は手法を追究する中で、「削る」「引っ掻く」「彫る」などの、絵具や物質を削ぎ落とす行為も積極的に取り入れるようになった。
同時並行的に、嶋は作家の「行為の痕跡」を意図的に画面に残すようになる。大きな作品は、下書きとしてのアウトラインをキャンバス上に描いたのち、上からプロジェクター等で画像を投影して描かれているものだが、近作では下書きとして描かれた線と、その上から描いた複数の輪郭線が混在している。ここからは、作家が描いてきた時間的なレイヤー状の構造を見ることができる。近作である、デニム地の布を漂白していくことで描かれた作品群は、描く行為が画面上に物質を加えることではなく、漂白剤の痕跡を残す行為であるという点において、作家による「行為の痕跡」について多角的に追究した結果の作品であるということができるだろう。
***
Touch作品を一連の流れから振り返るとき、当初「筆致」の意味を重ねられていた「Touch」は、徐々に筆で描くことを逸脱した多くの手法へと広がっていったことがわかる。この多岐にわたる手法から本質を見ようとするならば、必要なのは個々の要素を分解・分析することではなく、「なぜこれだけの行為のバリエーションが獲得される必要があったのか」を問うことだろう。また手法の探求の一方で、このシリーズの制作が開始された当初より「写真(画像)を見る」という揺らがない行為、さらに「資料写真」という特定の出発点は一体何を意味するのか。
ここ10年ほどの携帯電話やインターネットの飛躍的な発展によって、生活における存在感を増し続けるように思われる写真(画像)は、質量を有さないデータ上の「情報」である。嶋は「写真や画像の中からすくいあげられるイメージ」を「幽霊」に例える。そこには二つの意味が重ねられているように思われる。
一つは、写真(画像)が、世界の一部だったにも関わらず、世界との密接な関わりを断ち切られた存在だという点において。画像検索で得られる画像のグリッドは、公的・私的な写真が、時に無関係そうなもの(ノイズ)に至るまで、前後の文脈をはぎとられた独立したもののようにして並列している。一瞬の移動や複製(コピー)が可能な画像は、物理的・時間的制約からも解放された観念的な存在であると言えるだろう。
嶋の描く「資料写真」は、それ自体が本やキャプションというコンテクストから切り離されていること、撮られる段階で背景(コンテクスト)が排除されており、段階的に世界との関わりを断ち切られた存在であることから、インターネット上のさまざまな画像以上に観念的な(幽霊的な)存在である。
もう一つは、その存在が、自身の感覚に対する不確かな印象をもたらす点において。彼女の「写真の何を見ているのか」という問いは、「実体をもたない写真(画像)のイメージを受け入れている、<私>の感覚や認識とは一体何か」という自己に対する問いと言い換えることもできるだろう。そしてこの写真(画像)のもたらす「不確かさ」こそが、Touch作品の根幹にあるように思われる。
彼女にとってこの「不確かさ」は、論理的な解釈を与えることで解消される性質のものではなく、物質として身体を使って丸ごと受け入れ、咀嚼することを要する類のものであった。だからこそ、画家である彼女が、描く行為によって触れられる物質的な状態にすること(=「肉付け」)が必要であり、布や粘土などさまざまな質感や行為のバリエーションは、画面上に多くの質感をもたらすこと以上に、彼女自身が実感を得る行為として必要だったのではないだろうか。素材と手法をめぐる彼女の探求は、これからも続いていくだろう。
嶋は、同じモチーフに対してさまざまな手法でアプローチする。さらに近作で嶋は、作家の「行為の痕跡」を残すことで、作品が作家による一方的な解釈の提示になることを避けはじめた。このことは作品に、見る側の入り込む余地を少しだけ多く残すことになる。
資料写真と出会った時、嶋はそれを直感で「絵画的である」と感じたという。ここでの「絵画的」という言葉は、資料写真の「図と地」が明確であることを指した主に画面上のものであった。しかしこの、「わからないもの」に唐突に出会うという体験自体、一種の「絵画的な」体験と言い換えることも可能ではないだろうか。未知のものに出会うことは既製品に囲まれた生活の中では頻繁に起こることではないかもしれないが、生活の中に突如として「わからないもの」(例えば嶋の絵画のような)があらわれたとき、いかにしてそれを受け止めることができるのかは、個々人の選択に委ねられるところだろう。
広い世界を知覚するには、私たちに与えられた時間はあまりにも短い。だからこそ彼女の作品は、楽な方に身体を委ねていないか? と、画像という幽霊を見ることに慣れた緩んだ身体に、ちくりとした批評を与えてくれるのである。