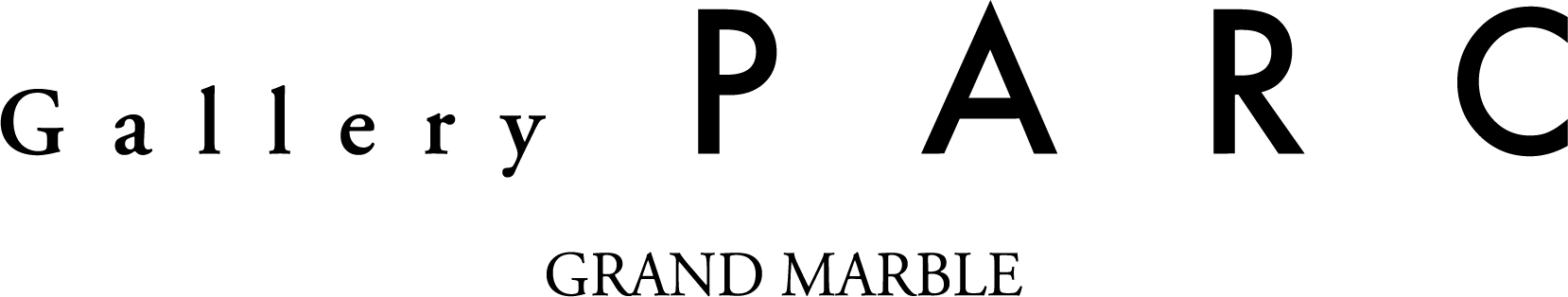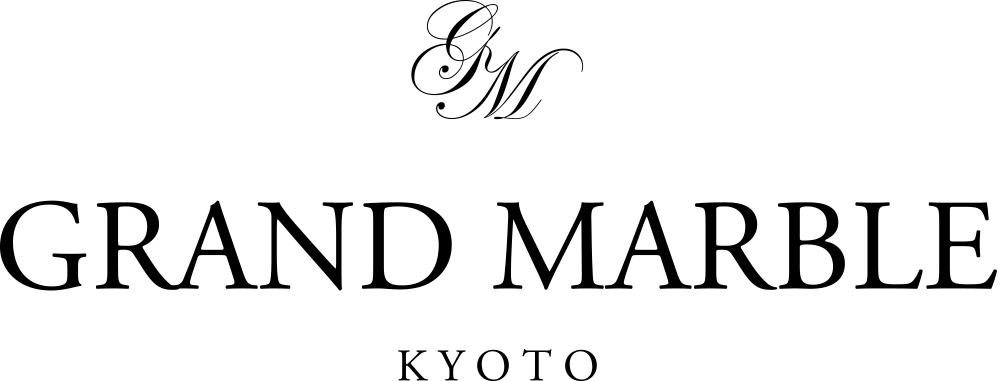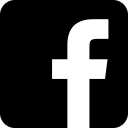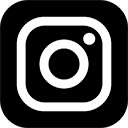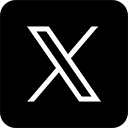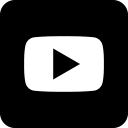「High-Light Scene」(2016)展示風景
High-Light Scene
平田剛志(展覧会「High-Light Scene」キュレーター / 美術批評)
ハイライト映像(シーン)を見るとき、私たちは何を見ているのだろう。今日の一日や過去を振り返るとき、私たちは何をハイライト(想起・回想)しているのだろう。そのとき、ハイライトするのは重要な部分を編集・抜粋した出来事なのか、あるいは「光」なのだろうか。
ハイライトシーン(High-Light Scene)は、映像において最も重要な、または感動的な場面、見所を要約した映像である。映画やドラマ、演劇のあらすじ、コンサートからスポーツの得点シーン、ニュースまで「ハイライトシーン」を通じて私たちは物語や試合、出来事の内容、結果を知ることができる。転じて、ある一日または旅行や祭り、冠婚葬祭などにおいて印象的な出来事やエピソードを「ハイライト」と呼び、過去を想起・回想するだろう。そう、「ハイライト」とは、過去を照らす光なのだ。
一方、ハイライト(HIghlight)とは、絵画において光のあたった最も明るい部分を白や黄色の絵具などで浮き立たせる技法である。光沢やテクスチュアを再現・模倣する表現技法として15世紀のフランドル絵画において確立され、現在では写真やマンガまでハイライトが効果的に使われている。
だが、絵画において、「ハイライトを置く」「ハイライトを入れる」「ハイライトをつける」などと表現されるように、「ハイライト」は絵の具という物質を意味する。つまり、ハイライトとは、モチーフに光(ハイライト)を象徴する白や黄色の絵の具を加筆・着彩することで、画面や対象の光の反射・反映を再現、視覚化する技法なのである。
このように、「ハイライト」には、一方には非日常的、劇的、重要な見所、他方では空間や人物にあたる「光」のテクスチュアを再現・模倣するという異なる意味があるのだ。つまり、「ハイライト」には、岡田温司が「ハイライトの逆説」【註1】と呼ぶように、二面性があるのである。「ハイライト」は自然な光の再現描写だが、ハイライトそのものは白や黄色の絵の具の塊りでしかない。鑑賞者は人物や物質に反射・反映する「ハイライト」を見ているのか、絵の具の塊を見ているのか、ハイライトは絵の具の物質として知覚されてしまう可能性を孕んでいるのである。「ハイライト」の像であると同時に物質である再現性と物質性、模倣と反模倣、フォルムとアンフォルムの二面性、二層性は、現代美術、モダニズム絵画へと連なる問題として今日に引き継がれ、今展における3人の作家にも確認することができる。
大洲大作(1973年大阪生まれ)は、主に列車の車窓を過ぎる一瞬間の光のシークエンスを捉えた写真作品を制作してきた。大洲の《光のシークエンス》は、具体的な車窓の風景でありながら、写真にとらえられることによって初めて見ることのできる「ハイライトシーン」である。では、列車ではなく日常において、大洲は「ハイライト」をどのように撮影、記録してきたかを本展では見ることができるだろう。また、スライド映写機を用いたスライドプロジェクションも出品される。スライド映写機を通じてスクリーンに映し出される「光」は、「それはかつてあった」【註2】光のハイライトシーンであり、映写機の光と音が私たちをかつての「光」へと誘うだろう。
竹中美幸(1976年岐阜生まれ)は、水彩、アクリル樹脂を用いた平面・立体作品を手がけ、(半)透明素材を介在した光と影、重層的な視覚の揺らめき、瑞々しさを視覚化してきた。近年は映画フィルムを素材に、暗室の闇のなかでフィルムに光を留めた作品を制作している。映画フィルムというシークエンスに刻まれた色彩は、展示空間に差し込む光と混ざり、揺らぎあう。本来、映画フィルムは映写機にかけられ上映されるが、竹中の作品は映写されずに天井部から吊るされたり、アクリルボックスに入れられて展示される。そのフィルムの静止は映画フィルムが生産中止され、映写・上映されないメディアとなった「現在」を体現してもいるだろう。竹中は、映画フィルムを映写機の光源からギャラリー空間に差し込む自然光へと変えることで、映画フィルムをリバ
イバルさせるのだ。と同時に、ロラン・バルトが「映画は挿話の連結であり、(中略)完璧な瞬間の総和から成る連続的な歓喜がある」【註3】と述べたように、映画フィルムがこれまで留めてきた光の「ハイライトシーン」を体現するのである。
中島麦(1978年長野生まれ)はストロークの集積・蓄積から生まれる絵画やドローイングを発表してきた。近年は、ドリッピング、ポーリングによる偶然性を取り込んだ絵画制作を行なっている。中島の作為と無作為、偶然と必然、カオスとコスモスがせめぎ合う画面は、描く行為の痕跡と絵の具の物質性が刻まれた「ハイライトシーン」である。今展では、新作のキャンバス作品および大洲大作の写真作品を素材とした新作ドローイング(5/4に公開制作)を出品する。
中島のドリッピング、ポーリングによる「一振り」は「一瞬」の集積であり、時間の層である。中島の絵画における絵の具の「ハイライト」は再現や模倣が目的ではなく、絵の具の物質性と描く身ぶり、速度の身体性を体現する。画面には筆とキャンバスが触れていないために筆触が見えないが、絵の具という物質を速度という一瞬の出来事(ハイライト)に還元した「ハイライトシーン」なのだ。一方、ドローイングには再現性と抽象性の境界域を描き出すハイライトの二面性を見ることができるだろう。
3作家に共通するのは、直接的な手を介さないで生まれた「ハイライト」であることである。大洲はカメラで「光」を撮影し、竹中は暗室のなかでフィルムに「光」をあて、中島は筆をキャンバスに触れずに「ハイライトシーン」を描く。「ハイライト」は人為的に「光」を再現・模倣する技法として生まれたが、3人の作品における「ハイライト」は再現・模倣するよりも瞬間的で偶然な「光」との出会い、その出来事、一瞬間、直接性の「ハイライトシーン」なのだ。
ゆえに、彼らの作品は支持体や素材という物質が反射・反映する「ハイライト」である。大洲のスライドフィルムや印画紙、竹中の映画フィルム、中島のキャンバスや絵の具は、「光」をとどめ、私たちへと反射・照射される「ハイ-ライトシーン」だ。「ハイライト」が反射・反映される本展において、私たちは何を見るのだろうか。私たちそれぞれの「ハイライトシーン」のはじまりである。
【註1】岡田温司『絵画の根源をめぐって』>PDF
【註2】ロラン・バルト『明るい部屋――写真についての覚書』みすず書房、1985年
【註3】ロラン・バルト『第三の意味』沢崎浩平訳、みすず書房、1998年、147頁。