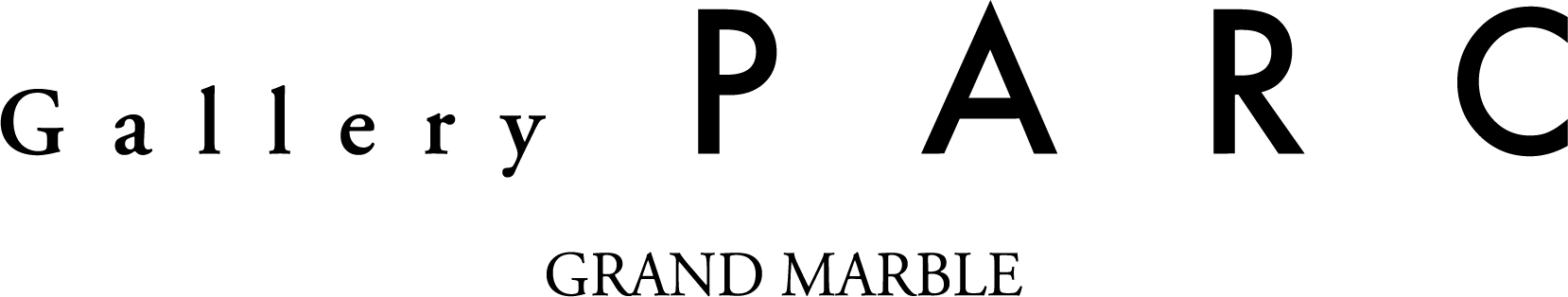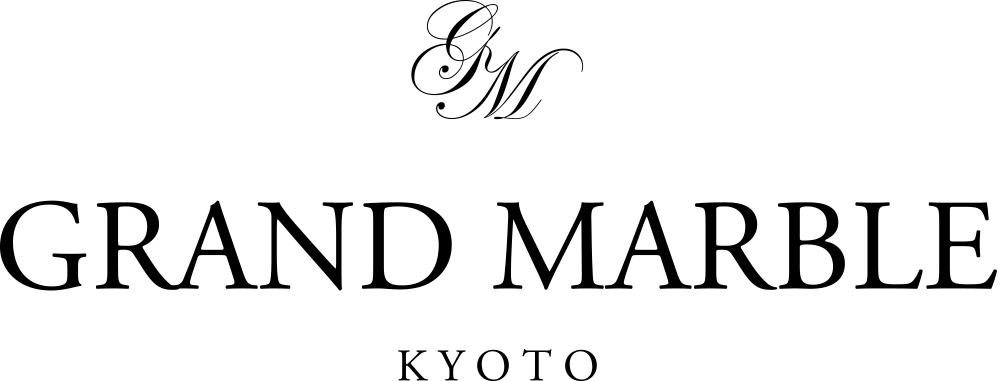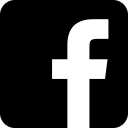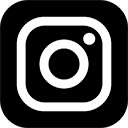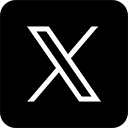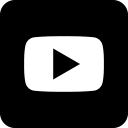「薬師川千晴:絵画へ捧げる引力」(2015)展示風景
「引力」に捧げられた絵画
武本彩子(京都芸術センターアートコーディネーター)
水彩絵具でもアクリル絵具でもいい、チューブから、手近な紙に少し中身を出してみてほしい。別の紙を重ねて絵具の塊をつぶし、紙をはがす。ほとんど同じような、それでも少し異なる二つの絵具の塊の表面をよく見れば、枝分かれした細かな筋がいくつかの層になって生じているはずだ。
絵具を置いた紙に別の紙を押し当ててはがし、細かな模様を画面に出現させる絵画技法、デカルコマニーは、1935年、パリのシュルレアリストのグループに参加していた画家、オスカール・ドミンゲスによって考案された【註1】。作家の恣意性の及ばないオートマティックな表現を求めるシュルレアリストたちの中で、この技法は多くの作家たちの関心を集め、いくつもの作品が生み出される。ドミンゲスの作品では、岩窟や廃墟のイメージを喚起させるものとしてこの技法が印象的に用いられている。
薬師川千晴は、一部の彫刻作品を除き、京都精華大学大学院在学中から一貫してこのデカルコマニーの技法を使用して制作を続けてきた。油絵具を重ね、同手法で得られた絵具の載った二つの紙片をシンメトリーに配置する初期の作品、そこから発展し、紙片の数を増やして放射状に配置した作品(完成ののち矢を射った作品もある【註2】)、紙片をランダムに配置し、四角に近い画面を形づくる近作を経て、今回は2種類の立体的な作品が発表された。
結果的に出てくる作品の形状は異なるものの、薬師川の作品のほとんどはデカルコマニーの技法が軸となっている。見いだされて80年が経つ、教科書にも載るポピュラーなこの技法、似たような模様を誰でも出現させることができる(そもそも「転写」を意味する)この技法に、彼女の作家としてのキャリアとオリジナリティが重ねられているということに、少し違和感があるかもしれない。それでも薬師川が一貫してこの技法を用いるのは、この技法に、単なる技術を越えた、はるかに重要な意味を託しているからだ。
薬師川は、デカルコマニーを絵具と絵具の「引力」を生じさせるための方法として用いる。ここでの「引力」とは、限定的な意味で用いられるのではなく、質量をもつ物質が本来的に備えているはずの、他を引きつけるエネルギーによって、物質と物質の間に生じる力を広範囲にわたって示しているようだ。彼女によれば、絵画にとっての引力は絵具と絵具の間に生じている。「引力」という概念から展開される、彼女の壮大な世界観には、圧倒されると同時に魅力を感じる。
ただ、薬師川の作品をよく見れば、「絵具と絵具」の結合のみが彼女の作品における「引力」ではないことに気がつかされる。表面の模様に現れた力のベクトルは、見方を返れば逆方向のベクトルとなる。張り付いた磁石をはがそうとする時に初めて指先に磁力の存在を感じるように、見えない力が意識されるのは、それとは逆の力がはたらく時だ。絵具同士に引力がはたらくならば、それと反対のもつ力、つまり紙(支持体)と絵具の結合という「引力」があってこそ、絵具の塊ははじめてイメージとなり、絵画となることができる。絵具と絵具、絵具と紙の結合といった複数の要素への気づきが、彼女の作品を平面から立体へと近づけてきたように思われる。
今回の個展で出品された作品は、薬師川が近年取り組んできた、緩やかに湾曲し、中央でシンメトリーに固定された立体に、対になった紙片が対称に配置されたものと、そこから発展した、長方形の紙を重ね、うねるように湾曲させた立体にランダムに紙片を配置したものの、二つのシリーズの作品群である。前者の作品では、油絵具によるデカルコマニー技法によってつくられたなめらかな表面の模様に、奥へと(あるいは外へと)向かう力を感じることができる。原色を中心とした鮮やかな色彩と軽いフォルムは、あでやかな熱帯の蝶や、仮面を連想させ、プリミティブな印象を与える。対称なものに生物の面影を重ねてしまうのは、対称に生まれついた人間の性だろうか、あるいは、葉脈や血管といった有機的な存在を表面の模様に見てしまうのは、絵具自体がかつて生物の体だった事を思えば自然なことだろうか。
後者のうねる紙を重ねた作品群は、前者から発展し、絵具と絵具の引力をさらに強く意識させるための形体として考えることができる。この作品の一部には、油絵の具よりも強い粘着力をもつテンペラ絵具が使用されている。書物から着想したというこのシリーズで、薬師川は一部に自作の土絵具を用いることによって、長い時間軸を画面に固着させることを試みる。それは、書物が人類の歴史の蓄積であるということを連想させる一方で、書物が紙とインクの集積である(でしかない)ことをも逆説的に匂わせる。表面に見る者の視点を泳がせ、付随してくるさまざまなイメージと戯れることを可能にする薬師川の一連の作品群は、絵具のもつ「引力」の一点において、揺らぐことのない一貫性を保っている。
絵画が神を語る時代が過ぎ去り、絵画の神性が失われて長い時間が経った。写真が技術を追い越し、画面が黒く塗りつぶされ、キャンバスが破られたそのあとで、私たちはすでに、絵画が紙(布)と絵具の塊でしかないことを知っている。それでもなお、絵画によって、自然や人間を、歴史や文明を語ることは可能だろうか。私たちはどこまで、まだ「絵画」を信じることができるのか? そんな問いにさらされる時、薬師川の作品のもつ「引力」は、残された一縷の望みとなるのかもしれない。
【註1】濱田明、田淵晋也、田上勉『ダダ・シュルレアリスムを学ぶ人のために』(世界思想社、1998年)p.117
【註2】詳しくは、前回の薬師川千晴個展『絵画碑』展覧会評、平田剛志「碑文̶絵画碑に寄せて」をご参照ください。>詳細はこちら