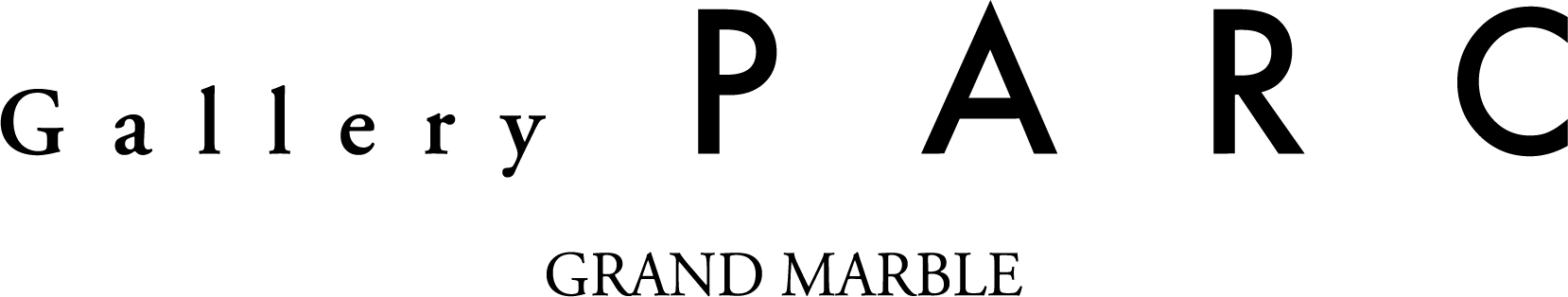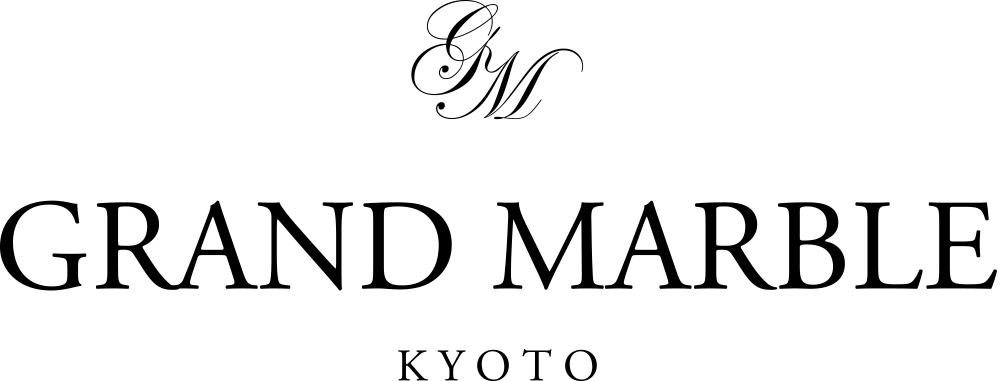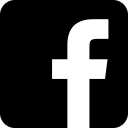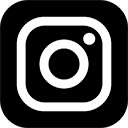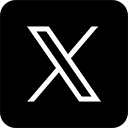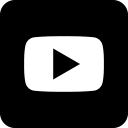Ishiba Ayako, Tada Keisuke, Yokoyama Nami
Exhibition info
大学協力展:愛知県立芸術大学
-パースペクティブカスタマイズ-
多田 圭佑
横山 奈美
2015.6.16. 〜 6.28.
Statement
意識しているわけでもないのに、ふっと目を引くものが多々あります。
それは誰かの服の模様だったり、道に落ちているモノだったり様々ですが、反射的に目がそれらに向きます。その時は色だけが目に入り、それには物質の厚みや重なり、二次元三次元もありません。色が目に入った後で、厚みや重なりなどまわりが見えて、そこでやっと服だと認識するのです。
何かが目を引き、それが○○だと認識するまでの時間、もしくは目に入った情報(色)とモノそのものに対して、わたしは何かしらのズレを感じています。
そのズレとは一体何なのか、そもそも我々は何をもってモノをモノと見ているのか。
虚実の入った風景を提示することで自分たちに見えているモノが何なのかを問いていきたいです。
石場 文子
在ることと無いこと、本当と嘘、相反する事柄の間にある曖昧な状態やことに興味があります。
フラットなディスプレイの中に広がる情報や現実と見紛う空間壁面に残るテープやステッカーの痕跡、そこに貼られていたポスターを想像すること。
そこに在った、存在した、ということが作品を作っていく切っ掛けになっているのです。
その関係性を多方から示すことは、“存在”とは何かを明らかにする手がかりになると考えるからです。
多田 圭佑
中学生の時にブリトニー・スピアーズに、高校生の時はキルスティン・ダンストに憧れていました。
いつも憧れは外国人で、濃い化粧をしてウィッグを被れば、そうなれると思っていました。
休日は街へ出てギャルショップに行き、緊張しながらお小遣いでミニスカートとチューブトップを買いました。ゴシップ雑誌を見て化粧を練習しました。
頑張りましたが、ブリトニーにもキルスティンにもなれませんでした。鏡を見て、なれないのに憧れ続ける自分に何度も落胆しました。
現在は、絵画制作をしています。
どうしようもない自分と重なり合う、少し悲しいものたちを日常から見つけ出し、それを描いています。そのモチーフが、ただの悲しいものから壮大なものや風景に見える瞬間があります。
その瞬間をずっと留めておくために描いています。
横山 奈美
About
本展はギャラリー・パルク会場提供による協力展として、愛知県立芸術大学油画専攻の在学および卒業生による展覧会として、同大学准教授である美術作家・大﨑のぶゆきのオーガナイズによるもので、昨年に続き2回目の開催となります。
「ラグランジュポイント=天体力学における円制限三体問題の5つの平衡解。いくつかの力(ベクトル)が釣りあった(打ち消しあった)場所」とする本展は、「いまだ未分化とも呼べる《現在進行形》の若い作家達の視点に注目する」ことを趣旨として、彼らが日本の中間地点「愛知」という場所で思考し、表現しつつあるものを紹介することでその「視点」を考察する試みに主眼を置くものです。
2回目となる本展では、その副題を「パースペクティブカスタマイズ」として絵画や版画を制作する3人の作家を紹介いたします。
2014年に京都嵯峨芸術大学造形学科版画分野を卒業後、2015年より愛知県立芸術大学美術研究科博士課程 油画・版画領域に在籍する石場 文子は、日常の中で錯視的に見る「面」に注目し、シルクスクリーンや写真を用いて恣意的にこの視覚に介入するかのような作品を制作しています。2010年に愛知県立芸術大学を卒業、2012年に同大学博士課程 油画・版画領域を修了した多田圭佑は、たとえば壁面に残るテープやステッカーの痕跡を「絵画」として再構築し、これらの存在について思考する絵画を制作しています。同じく2012年に同大学博士課程 油画・版画領域を修了した横山奈美は、生活の中にある「少し悲しいものたち」の姿を大正~昭和初期の「日本の洋画」を想起する重厚な画面として描き出しています。
彼らの視点とは絵画や版画といったメディウムを基盤に「歴史」「空間」「眼差し」を日々の視点で再構築し、見慣れた風景を新たな風景にカスタマイズして、描くための消失点を見いだそうとする試みでありその未完成さを置いても個々の表現や取り組みには、現在のアートシーンにおける「東京」や「京都」「大阪」といった地の影響の少ない、未だ大きな文脈に位置づけ難い特殊な表現の様相、あるいは様々なベクトルの「中間地点」としての愛知が持つ特性を垣間見ることが出来るのではないでしょうか。
【オーガナイズ】大崎のぶゆき(愛知県立芸術大学准教授)
【主催・企画】愛知県立芸術大学 大﨑研究室
【協 力】Gallery PARC
Introduction
本展は、愛知県立芸術大学油画専攻の在学および卒業生による展覧会として企画したものであり、彼らが日本の中間地点「愛知」という場所で思考したこと、表現しつつあるものを紹介することでその「視点」を考察する試みです。
「愛知」にはいわゆる日本のアートシーンにおける「ラグランジュポイント※」として独自の空気感と表現に対する意識が存在しています。
それは「西」と「東」の「中間」に位置するという対比構造や地理的条件などの影響をも含め、様々な引力の中間地点とするベクトルが均衡した特殊な「重力場」のようであるといえ、この特徴はこれまで愛知県立芸術大学出身者を含めた愛知をルーツとする多くの作家達が活躍する中で注目されるものでしたが、現在ではあまり触れられることがないように感じます。
2回目となる本展では、副題を「パースペクティブカスタマイズ」として絵画や版画を制作する3人の作家を紹介いたします。
石場文子は彼女の日常の中で錯視的に見る「面」に注目し、シルクスクリーンや写真を用いて恣意的にこの視覚に介入する作品を制作しています。石場は街で見かける赤いコーンや服のストライプ、看板といった物から視覚的な認識のズレが発生し、色面や柄面に見えたことから「見る」こと「認識すること」という私たちの視覚認識に問いかける作品を制作しています。今回の出品作は部屋のソファーを写した写真作品ですが、一緒に写される「色面」が錯視的にクッションやカーテンに見えるという風に恣意的に視覚に介入することで私たちの認識ズレ、視覚のズレをあらわにしています。
多田圭佑は壁面に残るテープやステッカーの痕跡を「絵画」として再構築し、これらの存在について思考する絵画を制作しています。今回の出品作「existence」のシリーズである「sticker」「wood」の平面作品は、木の板やフローリングにシールが貼られたように見える作品です。一見、ただそれだけに見える表面であるが、実はこれらのすべては「絵具」の集積で作られており、画面に絵具が乗る、イメージがある、という絵画の基本的事項に対して、表象の問題やイメージの問題を唯物論的に問い直しながらその存在について思考しています。
横山奈美は大正~昭和初期の「日本の洋画」を想起する重厚な表面を持ちながら、生活の中にある「少し悲しいものたち」を描き出します。
横山は「ブリトニー・スピアーズになりたかった、憧れは外国人で、濃い化粧をしてウィッグを被れば、そうなれると思っていました。」と語る憧れや願望が、大人になって「そうなれると思っていたけど、なれない。」という、あらがう事の出来ない文化的・人種的な相違に対し、彼女が日本人として、また絵描きの視点から自身の歴史性にベクトルが向いたことが契機となって一連の絵画作品を制作しています。彼女が敬愛する岸田劉生といった大正~昭和初期の「日本の洋画」をイメージする重厚な表面をもちながらも、その重厚さのイメージから相反する「もやし」や「トイレットペーパ」といった「少し悲しいものたち」を描く彼女の視線はひょっとすると私たちのポートレイトなのかもしれません。
彼らの視点とは絵画や版画といったメディウムを基盤に「歴史」「空間」「眼差し」を日々の視点で再構築し、見慣れた風景を新たな風景にカスタマイズして、描くための消失点を見いだそうとする試みであります。様々な表現がある中で「絵画」や「版画」を基軸に据え、思考する彼らの方法論の中から「ラグランジュポイント」としての魅力を見る事が出来ればと考えています。
大﨑 のぶゆき