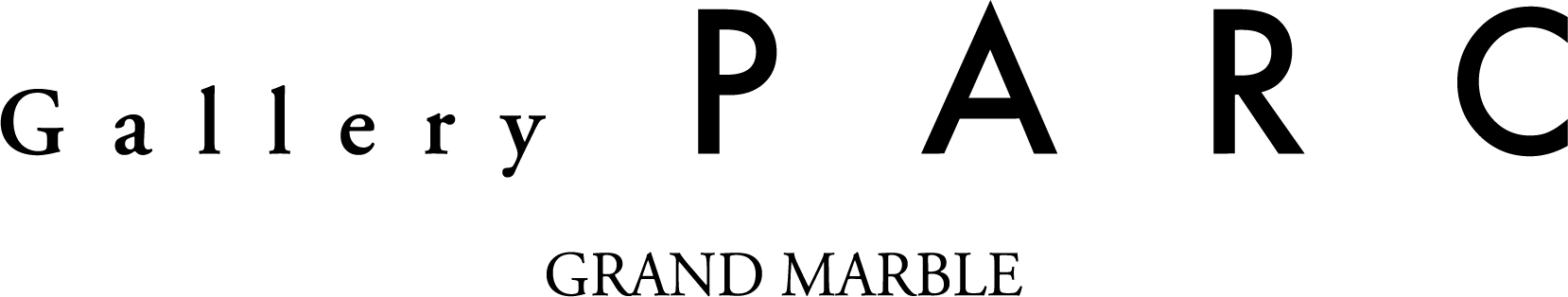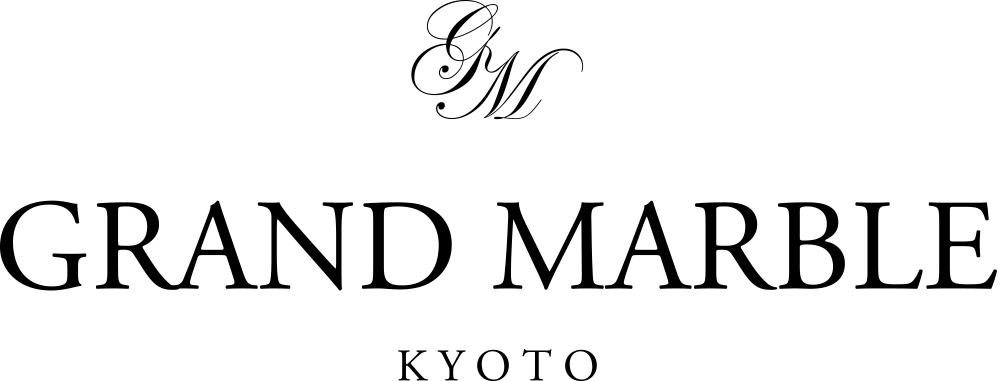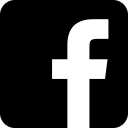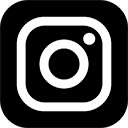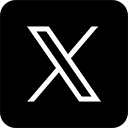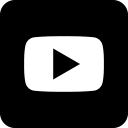「宮田彩加:裏腹のいと」(2016)展示風景
「枠」の外の空白 ― 宮田彩加展『裏腹のいと』に寄せて
武本彩子(Gallery PARC)
宮田彩加は、京都造形芸術大学大学院在学中に、手刺繍による作品制作に並行して、家庭用コンピュータミシンを制作に導入した。以降の約5年間、彼女の作品は専らコンピュータミシンを使用してつくられている。
現在のミシンは、経験の有無に関わらず誰でも同じように縫い上げることができ、もはや人の手を必要としないほど半自動化されている。そのような機械を前にして、「私にしかできないこと」を追求した宮田は、ミシンに読み込ませる画像データに「エラー」としての空白を与え、針目を飛ばす手法(のちに「WARP」と命名)を編み出す。データ上の空白は、作品では糸の横並びとしてあらわれ、糸の物質性が文字通り「前景化」する。
さらに、針目を細かくし、糸のみで刺繍する手法(のちに「Knots」と命名)を編み出した。布という支持体をなくすとともに、これまでの作品が抱えていたサイズの制限からも自由になり、近年は比較的大きな作品も制作してきた。
近作《VISION》は、現存する最古の絨毯とされる「パジリク絨毯」から着想を得た作品である。「Knots」の技法でつくられたペルシャ絨毯には、世界地図を模した欠損部分が意図的に生み出されている。新作《MRI》は、宮田自身の頭部のMRI画像を用い、空白に映る頭蓋の部分に、ゼンタングル(単純な図形を連続させ、パターンをつくっていく描画手法)によって装飾を加えた図像がもとになっている。
コンピュータで予測された未来の形を、いかにして裏切るか。そのような観点から彼女の技術は編み出された。しかし、それを繰り返せば繰り返すほど、作家は完成形を予期できるようになる。それはつまり、作家の思考自体が「コンピュータの一部」として連続するプロセスとなってしまうことである。宮田の制作は、ミシンという機械との協働であると同時に、終わることのない競争でもあるのだ。世界地図のアフリカが実際のアフリカ大陸ではないように、あるいはMRIが本当の頭の輪切りではないように、人は図像を記号や象徴として見ている。前作よりも抽象性を高めた《MRI》シリーズは、鑑賞者によっては顔や仮面、内臓にも見えるという。近作では、技術的な競争の構造に、人の「認識」という視点を導入しはじめている。
* * *
その名前自体がそもそも「sewing machine=マシン」の訛りであったように、ミシンはそれまでの労働時間やコストを大幅に削減する革命的な機械として登場した。しかし、開発の過程では、職を失うことを恐れた者によって、試作のミシンが壊されることもあったという。
「コンピュータが人間の仕事を奪う」。そんな話題を近年頻繁に見かけるようになった。人工知能はこの先20年ほどで人間の知能を超えるという。人間より賢い知能がどんな時代をもたらすのか、人は確実に言い当てることはできない。しかし、産業革命以降、機械に人の仕事が奪われてきたように、現在人間がおこなっている多くの仕事が、近い将来コンピュータによって代替されるだろう。弁護士や医者の仕事までもが、ある程度代替可能になり、人にはできてコンピュータにはできない「創造的な」仕事だけが残るという。
日々の生活で、コンピュータはもはや欠かすことができない。コンピュータが扱う範囲はますます広くなり、一見すると私たちの可能性を広げ続けてくれているかのように思える。しかし実は、私たちの生活自体、思考自体が、徐々に「コンピュータで予測された未来」という「枠」の中に閉じ込められつつあるということはないだろうか。それはおそらく、人がコンピュータを生み出したとき、否応なしにくっついてきた「呪い」である。私たちが自ら確実に「選んだ」と思ったものも、実はコンピュータによって差し出された選択肢の一つに過ぎなかったかもしれない。
ミシンを「嫌い」と言い切る宮田が、それでも手刺繍や絵画のような、別の手法に向かうことをしないのは、そのようなコンピュータ(ミシン)の呪いを避け、「感性的なもの」に逃げ込むことをよしとしないからのように思われる。「創造的なもの」は、「感性的なもの」とイコールではない。創造的であるとは、技術、感性、労働といった領域を横断し、それらの外の空白を見つけることである。考えてみれば、一つの言語で語ろうとすること自体が、あまりにも「コンピュータ的なこと」ではないか。
呪いを解く方法とは、呪いの枠の外にある空白を地道に見つけていくことである。たとえそれが少し大きな「新しい枠」の中であったとしても、それでしか「呪い」を超える手段はない。宮田の作品は、これからの未来を考えていくための、ひとつの糸口を与えてくれるものではないだろうか。