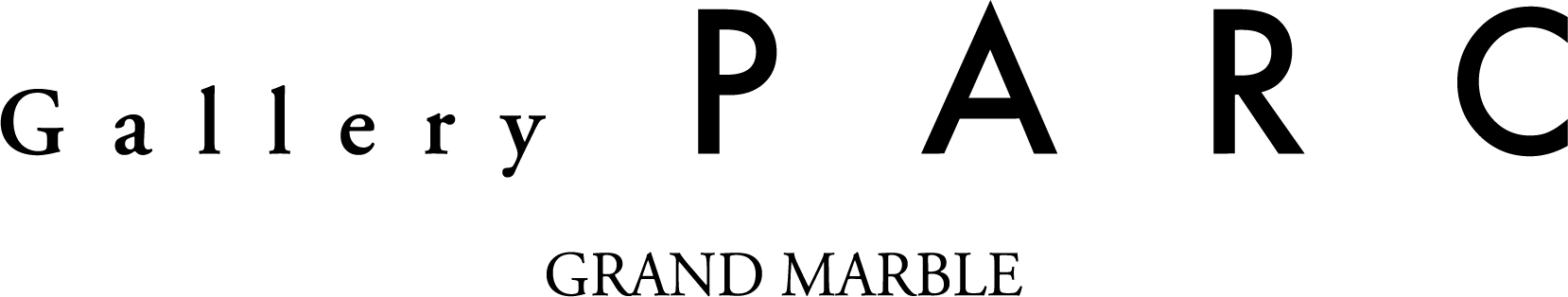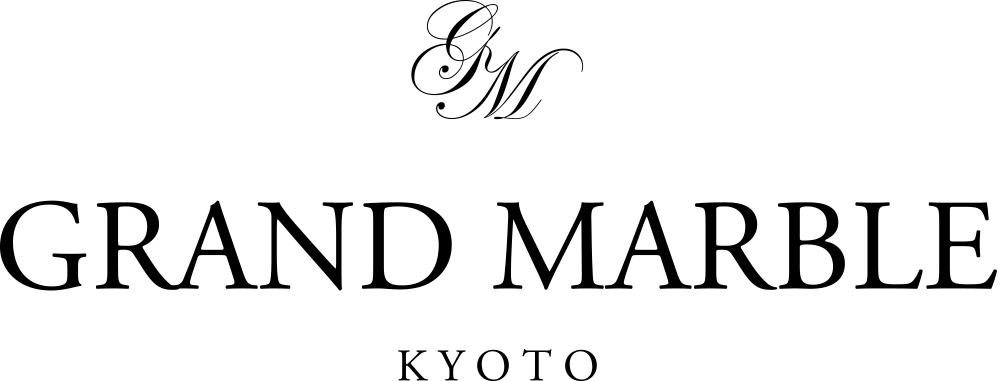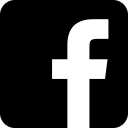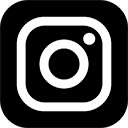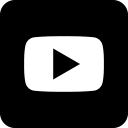2012
「藤永覚耶:とどまり ゆらめく」展示風景
ゆらめき IN THE AIR
平田剛志(美術批評、京都国立近代美術館研究補佐員) 2012/7/30
空間に色彩がゆらめいている。
そのゆらぎを初めて見たのは、2階建の一軒家を改築したギャラリーで開催された個展だった【註1】。ギャラリーを訪れたのは、夕刻を過ぎて暗闇が広がりはじめたころだった。1階には、「犬」や「森」といったモチーフが布にインクの点を重ねて描かれ、ライトボックスにマウントされた作品が展示されていた。図像は人工光によって均一に照らされ、ドットの色彩が発光するような作品だった。
続いて、2階に上がると、展示空間全体に緑のインクの点が森を思わせる抽象的な図像として描かれた《forest》(2011)が見えてきた。作品は天井から吊るして展示されており、ときおり開け放たれた窓から風が入り、夕闇の中で図像は揺らめいた。この《forest》は、1階の展示とは異なり、光や風など偶然性が取り入れられ、作品の様相が変化する「とどまり ゆらめく」空間が展開されていた。自然光のみによる展示のため、描かれた図像の細部は判別しがたいが、夜の森のような静かな存在感がある作品であった。藤永覚耶は、1階と2階の展示空間に光の安定と不安定、明るさと暗さ、図像の鮮明と不鮮明など相反する要素をダイナミックに展開し、図像が生成する瞬間に立ち会うようなイメージが強く焼きついた。
このように藤永の作品は現実の光景やものが起点となり、抽象的なイメージを展開する作品となっている。その制作プロセスは、写真によってモチーフとなる森や木などを撮影し、図像をアルコール染料インクで布地に点描し、最後に溶剤により図像を溶かすことで制作されている。撮影されるモチーフは、初期は靴やコーンフレーク、風景などの一部分をトリミングした画像を素材としていたが、近年は鳥や犬、《foliage》のタイトルのもと森や葉を題材に作品を制作している。
では、なぜ藤永は写真を素材に用いながら、写真の有する再現性を捨象するのだろうか。それは、藤永が「写真のピントが鮮明に合った箇所よりも、ボケやブレにリアリティを感じる。それは再現的なリアリティではなく、個人の先入観や価値観をぬぐい去った等価な世界に立ち戻るような真実味を持った感覚である」と述べるように、ボケやブレたイメージにリアリティを感じる点に由来している。つまり、ピントが合った鮮明な画像は、日常や個人の感覚、記憶などとつながり持った画像となるのに対し、不鮮明な画像は「個を離れ、空っぽの状態」で、画像が私性をもたない「等価な世界」としてのイメージを伝える点に真実を感じるというのである。
だが、ボケやブレた写真をモチーフとしたり、リアリティを求める絵画は、藤永だけでなく数多くのアーティストがさまざまに試みていることはここで触れずともよく知られている。藤永の試みが新たな視点を付け加えているのは、写真図像を点(図)に置き換え、固定化された点を再び溶剤で溶かすことで「ゆらめく」イメージを生成していることである。つまり、インクで色彩を画面に一度とどめながら、再び溶剤で色彩を混ぜ合わせる定着と浮遊を同一画面上で行っているのである。藤永作品の水彩画や水墨画を思わせる色彩の滲みや揺らぎは、このような「とどまり、ゆらめく」色彩のプロセスの結果なのである。
続いて、藤永の展示方法について述べてみたい。近年、藤永は光や揺らぎをもつ森や葉を素材に、その技法と支持体を密接に関連させている。例えば、冒頭で触れたように布地を空間に吊り下げて展示し、周囲の光や風を取り込んだ試みである。布は吊り下げられることで、張りや弛み、光の透過・浸透によって、作品の図像は一定せず、その存在を揺らがせることになる。
このような布地を吊り下げる展示は、2008年の個展「Alice Syndrome」の展示において、すでに壁に掛けるかたちで試みられている。壁面に布を固定しないことで、布の一部には襞や揺れが加わり、図像の色彩に物質の揺れが変化を付け加えることになった。その試みが大きく展開したのは、2009年に北海道根室市の旧落石無線送信所跡で開催された「落石計画第二期:scattered seeds 残響」である。廃墟となった旧落石無線送信所を会場に、藤永は布に染料インクでドローイングを施した《foliage -ochiishi-》(2009)を吊るして展示したのである。たしかに、これまでにもグループ展や個展で布の作品を壁面に吊るして展示することはあった。だが、旧落石無線送信所の空間では、窓辺の天井付近から4メートル近い布地を吊り下げ、窓から差し込む光が作品を透過する展示であった。続いて、2010年に「アーツチャレンジ2010」での愛知芸術文化センターの2Fロビー、愛知県小牧市の旧竹内邸・常懐荘を会場とした「STAY -常懐荘にて-」など、藤永はギャラリー空間ではない場所を会場に自然光や周囲の環境を取り込む展示を連続して試みた。それ以前の布地を壁面に展示する方法は、安定した照明や壁面が得られる空間内で布の性質をあらわにした。対して、「落石計画第二期」以降の布地を空間に吊り下げた展示は、光や風など周囲の環境を取り込んだ点に大きな違いがある。ここで藤永は、光と揺らぎを自身の作品に取り込んだと言えるかもしれない。
このような不定形な光と風の偶然性、環境を取り入れた展示の試みは、1966~74年まで南フランスを中心に活動した「シュポール/シュルファス」の作家たちの作品を想起させるだろう。例えば、布地を素材に吊り下げたり、垂れ下がらして展示する作家として、パレット形のかたちを規則的・反復的に描くクロード・ヴィアラ、粗織り薄布や布状のままのキャンヴァスを素材に規則的な点を描くノエル・ドラの作品が挙げられる。これらの作品は、作品を不安定、不均衡な状態に展示をすることで、展示環境の光や風の揺らぎを受けると同時に、絵画を見ることの制度をも揺るがすものであった。つまり、絵画が伝統的に抑圧してきた「表裏、張りと弛み、硬軟、しみ、浸透性、型」を取り入れたのである。さらに彼らは、路地や広場、穀物倉、海岸などに作品を展示し、伝統的な絵画観や展示方法を問い直す試みをおこなった。藤永もまたホールのエントランス、家屋や旧無線送信所など、ギャラリー空間とはおよそ異なる場所で作品を展開させてきた点に共通性が見られるだろう。
このように、藤永とシュポール/シュルファスとを比較したとき、多くの共通点がみえてくる。その最も大きな特徴は、支持体/表面(シュポール/シュルファス)への関心である。梅津元は「美術作品とは、視覚化と物質化のふたつの働きによって成立する」【註2】と述べているが、シュポール(支持体)とは物質化の問題であり、シュルファス(表面)とは視覚化に関わる問題である。つまり、シュポール/シュルファスとは、「イリュージョン性を打破し、物体がそれ自体として表現の強度を帯びることをめざす」活動であった【註3】。
藤永作品もまた、支持体に布地やパネル、近年ではライトボックスを用いるなど、支持体の特性と表面の図像が密接に合わさった構造を有している。たとえば、光を透過する布を支持体に用いて描画した後、布地を吊るして展示をすることは、布地に固定化された色彩を展示環境の中で再び揺らがせる試みであった。藤永作品にとって、表面の図像を絶対的なものとして固定化するのではなく、展示空間のなかで相対的なものとなることが目指されているのである。
ここで注意を要するのは、近年新たに始められたライトボックス形式の作品だろう。このシリーズは、これまでの作品とは異なり、人工的な光により均一に、安定的に色彩を照らし出す作品であった。藤永作品の特徴である揺らぎや光の変化はなく、異なるベクトルに位置する作品のように思えるかもしれない。だが、このライトボックスのシリーズもまた、藤永らしい支持体と表面の関係性が保たれている。このシリーズは、暗闇の中に展示をすることで、暗順応によって作品の見え方が変化することが意図されているからである。このように、藤永は、「とどまり ゆらめく」色彩の変容を支持体(物質化)と表面(視覚化)の2つを組み合わせることで視覚と物質の双方でゆらめきをつくり出しているのだ。藤永は支持体/表面に対する批評性をシュポール/シュルファス以降、正面から取り組んでいる稀有な作家と言えるのではないだろうか。
岡崎乾二郎は「見る者に対向している面、見ることが可能な面という、徹底して見ることに関わっている面を表面というならば、それに対して支持体はもっぱら「見えない」、「見られない」という事に関わってくるだろう」【註4】と指摘している。藤永は、シュポール/シュルファスと同じく支持体を「見える」ようにした。と同時に、藤永は「徹底して見ることに関わっている」表面にブレやボケたイメージを描き、溶かすことで「見えにくい」図像をつくり出す。見えているのは支持体なのか表面なのか、光なのか色彩なのか、「とどまり ゆらめく」空間は鑑賞者を静かに揺さぶりつづける。
【註1】「藤永覚耶 - into the water -」2011年9月16日~9月25日、GALLERY GOHON (名古屋)
【註2】梅津元「まなざしの解放」『シュポール/シュルファス展:1970年・南仏―パリ』読売新聞社・美術館連絡協議会、1993年、p.146
【註3】松浦寿夫「終わりなき反復」『風の薔薇』第3号、1984、p.9
【註4】岡崎乾二郎「現実について」『風の薔薇』第3号、1984、p.73