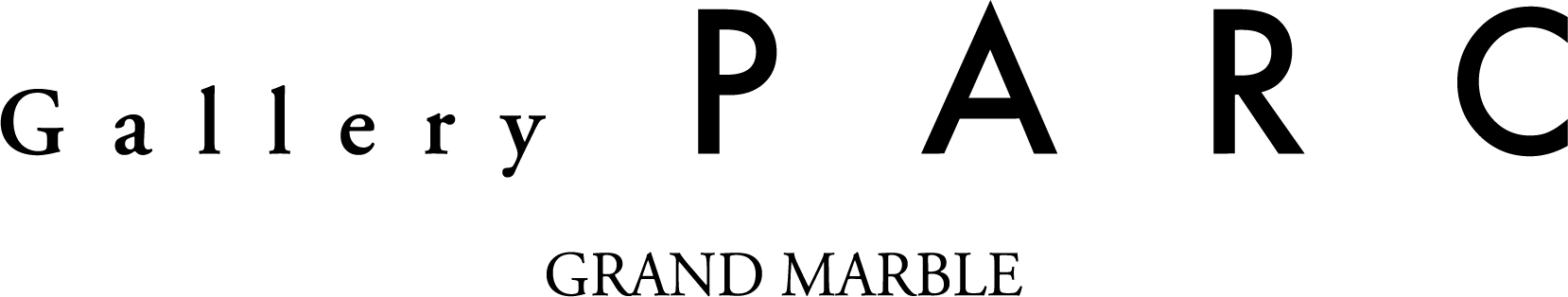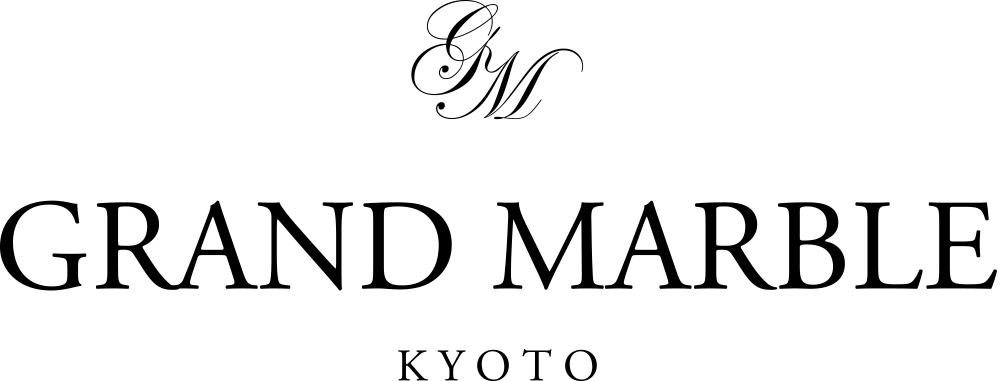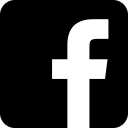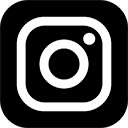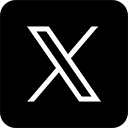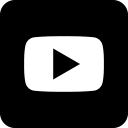Kusumoto Takami
Statement
「未知を取りこぼさないために」
何かを見るとき(捉えるとき)、ʻʻそれʼʼを捉える為の枠、フィル ター、物語(背景)を通してそれを見ようと(理解しようと)する。
その枠やフィルターは、経験や知識といったʻʻ既に知ってい ることʼʼ、ʻʻ知っていると思っていることʼʼをもとにつくられる。
昔に流行った3D立体視のステレオグラムやだまし絵のよう に、一度「見方」を知ってしまうと、最初に見ていた図像はも う見ることが出来なくなってしまう。
放送終了後のテレビ画面。
もしかしたら、あの砂嵐の中にあったかもしれない美しい (かもしれない未知の)イメージをもう私は見ることは出来ない。
About
楠本孝美(くすもと・たかみ/1985年生まれ・長野県)は、近年、転写や型取りなどによる「うつす」をプロセスに持った作品制作に取り組んでいます。しかし、その「うつす」行為は完璧なコピーを目指されたものではなく、むしろ楠本自身によって「うつせない」が生じ るように仕向けられているともいえます。
楠本は過去作《anoare》のシリーズにおいて、インクでイメージを描いたガラスの上にシリコンを流し込み、固め、引き剥がすことによってイメージを転写しています。しかし、インクの太さ・細さ、濃淡などの偶然によりインクは完全に転写されず、シリコン上にはうつし取られたインクと共に、うつし取れなかったインクの厚み(凸)に相対した凹みが生じます。ここではシリコンにインクという「物質」が移動する「うつす」と、インクという物質の「存在」を「うつす」ことが同時に起きているといえ、楠本が描いた(選択した)イメージは、意図と偶然、インクという物質とシリコンの凹みなど、その意味や在り方にズレやブレといった「うつしまちがい(エラー)」を含んだ「何か」として転写されています。 楠本の作品において、この「イメージと物質が統合されながらも、いつまでも分かたれている」という、いわば入れ子のエラーを同時に眺める状態は、後にシリコンの支持体に写真イメージを転写する《untitled》においても試行されています。ここではインクの定着における偶然性は排除され、あらかじめPhotoshop上で構成された画像イメージがシリコン(後にコンクリート)に転写されています。その後にイメージをシリコンごと(シリコンをイメージごと)部分的に削り取ることで、支持体の素地がイメージと綯い交ぜになった状態をつくり出しています。
本展出品作品《no_name》は、この支持体をシリコンからモルタルに変更して制作されています。制作はまず楠本の選択した画像イメージがPhotoshop上で加工されることからはじまります。その加工はコラージュ的なイメージの配置にとどまらず、色の濃淡や解像度の異なる同一画像の組み合わせ、ネガポジ反転のシャドー(のような)イメージを用いた遠近感や空間性の創出、ブラシ(筆)ツールを用いた加筆・消失などのデジタル上のテクニックを用いたモノクロ画像は、波板による凹凸を持ったモルタルに転写されます。また、この転写の過程ではモルタルの乾きに応じて、黒色に含まれているインクはCMYKに分離され、画面上に予期せぬ色彩を感じさせます。そして、凹凸の画面は見る位置や差し込む光によってイメージに関わり、顔料インクはモルタルと紫外線によって日々変化しています。これらは、いわば「静止画が再生された動画」のように、常に目の前に留まりながらも、認識が追いついたと思うとすぐに「何か」へと逃げていく体験をもたらします。
楠本はこうした作品制作にあたって『未知を取りこぼさないため』にという言葉を使います。私たちは常に「未知」と出会っているといえます。しかし、その「未知」は過去の経験や知識、形式や文法といった類型などから想像することで、瞬く間に「概知」として認識し、それに準じた最適な見方を当て嵌めます。また、この「未知から既知」へのタイムラグがあまりに瞬間的であるため、私たちは目の前の「未知」を自覚することは少なく、また、その認識や見方は一度獲得すると、およそ不可逆的に固定化されてしまいます。いわばこれは、記憶や経験のなかにある実体のともなわない認識の雛形を「オリジナル」として、そこに目の前の未知を当て嵌める、つまり未知をオリジナルのコピーにしてしまうことであり、ここで私たちは雛形に沿わない「未知」を取りこぼしてしまっているといえるのではないでしょうか。
楠本は作品によって『私たちの「見る」が、それがそれであると認識する前の状態に戻れること、あるいは少しでも未知に接する状態を留めること』を目指しているといえます。そして、そのことで私たちの「未知から既知」への認識が、何によって・どのように「つくられていくのか」を観察しようとしているといえます。これは、いわば「伝言ゲームの伝えまちがい」の経緯を観察することに似て、オリジナルが様々な人(媒体)を経て伝達(コピー)される過程で、それぞれの思い込みなどによる些細なエラーがどのように混入し、どのように帰結するのかを見ることで、私たちの認識がどのような因子や流れを持っているのかを知る手立てであるといえます。
本展において楠本は、ここに「イメージと物質を同時に眺めることができる状態」をつくりだすことで、より多様なエラーが起こる状態を作品の鑑賞につくりだそうと試みます。
作家情報について詳細はこちらよりご覧ください。 >Artist info