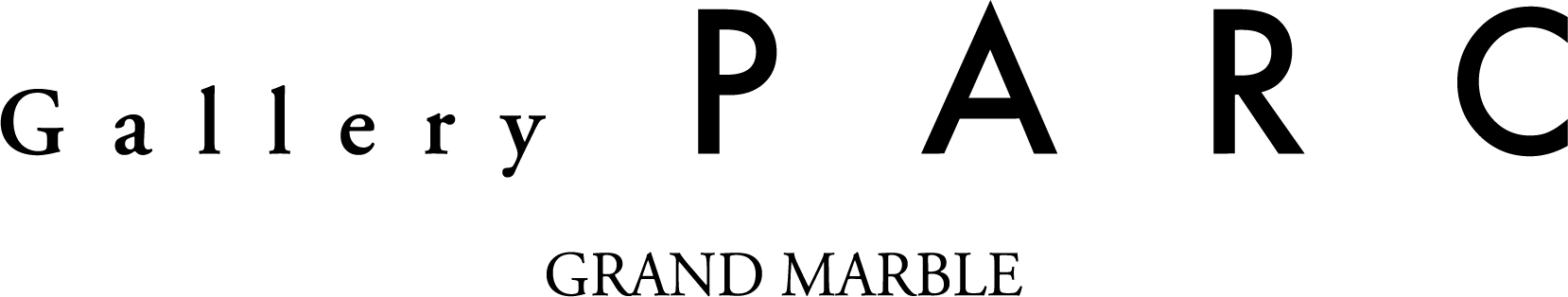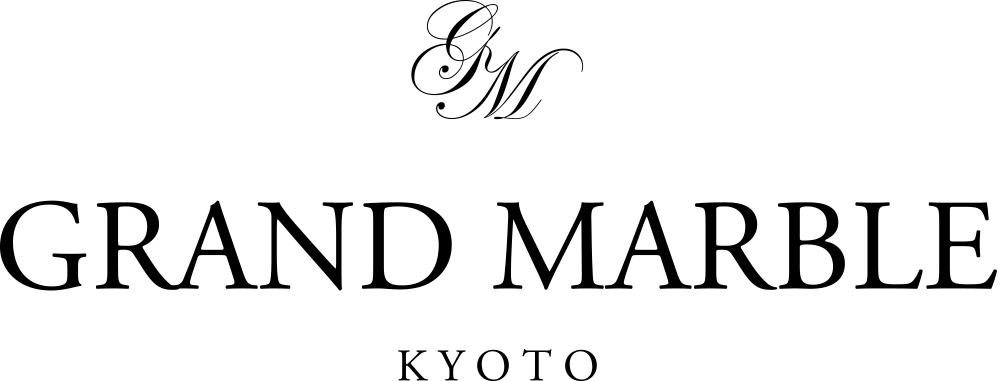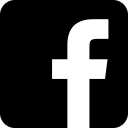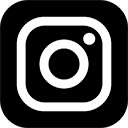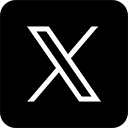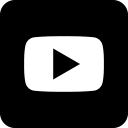Yoshimoto Kazuki
Statement
撮る人と私
私は原爆ドームにむけてシャッターをきる人々の姿に対して、最初は特に気にもとめていなかった。それは見慣れた光景だった。様々なモニュメントが点在する平和公園のなかでも原爆ドームは最も有名であり、爆発によって破壊された姿は初めてそこを訪れた人にとって、思わずシャッターをきりたくなるほどのインパクトがあると思う。
しかし、多くの人々が鞄からカメラや携帯電話を取り出し撮影するその様子を、少し距離をおいて一定時間眺めていると、少しずつ異様な光景に思えてきた。
路面電車を降り、横断歩道を渡り、原爆ドームにたどり着く、そして写真を撮る。
撮影する場所も、みんなだいたい同じ場所で撮影する。
この一連の流れがオートメーション化されたもののように見え、私はその様子を何枚か撮影した。当初はその一連の流れのほうに興味を持ち、原爆ドームもファインダーの中に入れ、「原爆ドームをとっている人」の情景として捉えていたが、撮影した写真を見直しているうちに、撮影している人の姿(性別、国籍、年齢、体格、服装、服の皺、髪の毛の色、持ち物、カメラの構え方、など)のほうがやたら気になり始めた。
そこで後日、原爆ドームを撮影している人の背後に気づかれないようにそっと近づき、後ろ姿のみを撮影してみた。
「これだ」っと思った。
About
2005年に日本写真映像専門学校を卒業、2007年に京都造形芸術大学情報デザイン学科を卒業、2012年に情報科学芸術大学院大学(IAMAS)を修了した吉本和樹(よしもと・かずき/1984年・広島県生まれ)は、写真をおもな表現媒体として、これまでに広島をモチーフに撮影をおこないながら、ヒロシマという場所に対して人々が抱くイメージや、その場所が持つ機能や力、そこに向けられるまなざしをテーマに制作活動を行っています。
吉本の初個展となる本展は、2011年より取り組んでいる、原爆ドームに対してカメラを向ける人々の後ろ姿を撮影したシリーズ《撮る人 A-bombDome》により構成します。
1945年に原子爆弾が投下された際、爆心地に残った産業奨励館という建築は、その残ったドーム状の鉄枠から「原爆ドーム」と呼ばれるものとなりました。その後、建築家・丹下健三の設計により1955年に設置された広島平和記念公園は、この原爆ドームを北の起点として、南に向かって原爆死没者慰霊碑、広島平和記念資料館が一直線に配されたもので、原爆ドームはいわばヒロシマのシンボルとして位置づけられたといえます。そして現在、広島市のみで年間におよそ1165万人、海外からだけでもおよそ65万人以上の旅行者がこの地を訪れ、そのほとんどがドームを目にし、そして、おそらくその大多数の人々がドームにカメラを向けているでしょう。
広島に生まれた吉本にとって「路面電車を降り、横断歩道を渡り、原爆ドームにたどり着く。そして写真を撮る。撮影する場所も、みんなだいたい同じ場所で撮影する」というこの光景は、とても見慣れたものだったといいます。しかし、ある時に「この一連の流れがオートメーション化されたもののように見えた」という吉本は、その毎日延々と繰り返される画一的な動きにどこか違和感を覚え、ある日、「原爆ドームと、それを撮る人」をひとつに納めた写真を何気なく撮影したといいます。しかし、撮影した写真を見返すうちに、次第にそこに写る「撮る人」の性別、国籍、年齢、体格、服装、服の皺、肌の色、髪の色、持ち物、カメラやその構え方などが当たり前に「違う」ことに改めて気付き、そこに純粋な興味を抱くようになったといい、後日に「原爆ドームを撮影している人の背後に気づかれないようにそっと近づき、後ろ姿のみを撮影してみた。」と言います。
「『原爆ドーム』を撮る人」への興味に端を発した吉本の視点は、「原爆ドームを『撮る人』」へと移り、《撮る人 A-bomb Dome》のシリーズ制作は始まりました。
吉本は、ここには言葉で形容しがたい独特な雰囲気があり、それは広島という街の隅々まで充満し、あるいはそれらについて考えた時にさえも、そうした雰囲気の存在を感じると言います。そして、その中心にはシンボルとして配置された原爆ドームがあると考えています。
今日までのおよそ70年に渡り、広島は「ヒロシマ」、産業奨励館は「原爆ドーム」と呼ばれ、その強い引力によって人々を引きつけ、訪れる様々な人々と歴史的なコンテクストを共有するための普遍的なシンボルとして、今も強力に機能しているといえます。
しかし、その引力があまりに強力すぎるが故に、ヒロシマやドームは私たちの目と思考を瞬時に引きつけ、「目の前のものをよく見る、目の前のものから思考する」という態度を瞬間的・永続的に停滞させてしまう要素をも併せ持つのかも知れません。
本シリーズの制作を通じて吉本は、原爆ドームの周辺にあるモノや人をありのままに観察することから、ここを覆う「雰囲気」に目を凝らし、その考察を試みています。また、それは目の前の光景を物語から解放し、鑑賞者をまず「見る人」に立脚させるものであるともいえます。
作家情報について詳細はこちらよりご覧ください。 >Artist info